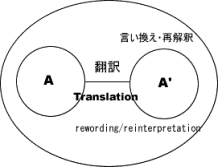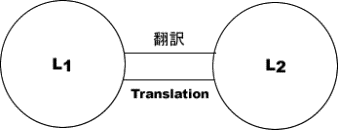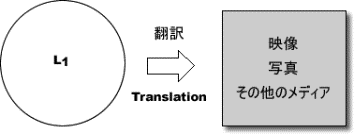文体形成のヴィークルとしての翻訳
一つの文化を超えて読まれる村上春樹
長 期に渡って多くの読者を魅了してきた古典と呼ぶには程遠いものの、村上春樹の作品は現代において多くの人々に読まれている。いつの時代にも同時代を代表す る作家はいたが、村上春樹という作家の特徴はその作品の多くが海外で共時的に多数の読者を獲得していることである。彼の全作品中 28 作がのべ 18 カ国で翻訳されており 、特に韓国、台湾、香港、アメリカではほとんどの作品が翻訳され、高い評価を得ている。例えば 1994 年にノーベル文学賞を受賞した大江健三郎のケースと比較するとより多くの国で村上春樹の作品が翻訳されていることがわかる。大江氏の場合は全 36 作品中 13 作品が翻訳されているが、そのほとんどが英語版であり、その他 8 カ国で翻訳されているだけ である。村上春樹は国内のみならず、海外にも多数の読者を持つという点で現代における代表的な作家の一人であると言える。
つまり、村上春樹作品の受容の特徴は日本という文化を超えて翻訳され、受容されていることである。その作品の文学的価値については、ドイツやフランスで論争を巻き起こしたり 、国内外で賛否両論あるものの、一つの文化を超えて読まれている点が村上春樹を現代における代表的作家とする所以である。
ともかく、村上春樹の作品は 1987 年に発売された『ノルウェイの森』が累計 600 万部も売れるなど、驚異的な数字を残している。
こうした受容と比例するように、村上春樹という存在は多くの人々を饒舌にさせ、未だ存命中の同時代作家であるにも関わらず多くの作品研究にインクが費やさ れてきた。多くの研究や評論の主たる関心は大まかに言って「なぜこれほどまでに読まれるのか」という命題であり、この問いに対して様々な文学理論や社会学 的アプローチにより分析がされている。しかし、その多くは what に関する部分である。つまり、作品中何が言われているかに関する部分の研究がほとんどである。本研究のアプローチは文体論的な how の部分に基づいており、作品を解釈することではなく、なぜ (why) 、また、どのようにして (how) 作品の意味が生じているかに関心がある。さらに翻訳における文体に注目した点にオリジナリティがある。先行研究にも作品の表現に注目した研究はあるが、加 藤典洋の『日本風景論』 に代表されるように、村上作品における特定の語彙やカタカナ語に注目したものであり、広い意味での文体に焦点を絞り実証的に検証した研究は少ない。
村上春樹作品は発表当時から文体に言及されることが多かった。三浦 [1982] の言うように、その物語の内容や展開よりも用いた言葉の新しさが特徴であった。その新しさは多くの評論が感覚的に評すところによれば、カート・ヴォネガットとの類似性が指摘 さ れたように、翻訳調や外国文学(アメリカ文学)との類縁性が問題とされていた。つまり、文体の異質性が問題とされつつも肯定的に評価されたのである。村上 春樹はいわば、文体の新しさと異質さによって文壇にデビューしたのである。そして、そのことを裏付けるように本人も以下のようなコメントを述べている。
(1) 「なるべく文章をシンプルにするために、僕は 最初の何ページかを実験的に英語で書いた 。もちろん僕の英語力はたかが知れている。高校生の英作文程度の稚拙な文章である。でも、書こうと思えば本当に基礎的なシンプルな語彙だけでも文章が書け るんだという発見をしたことは、僕にとって大きな収穫だった」 (強調引用者、以下同じ)
こ れは 1979 年のデビュー作『風の歌を聴け』を書いたときのことであるが、この作品は結果的に日本語で発表された。つまり、英語で書くという行為によって一旦母語から 離れ、その異質な表現を再び母語に変換するという営みを行っていたのである。つまりは、「翻訳」という行為によって自らの文体を構築しようとしたのであ る。村上は言う、
(2) 「十代の頃だけれど、もし英語で小説が書けたらいいだろうなって考えていた。日本語で書くよりも、英語で書いたほうがずっと正直にストレートに自分の気持 ちが書けるような気がしたんだ。でも僕の英語力じゃそんなことはとても無理だった。だからなんとか日本語で小説が書けるようになるまでには随分長い時間が かかった。だからこそ僕は二十九になるまで小説というものは一切書けなかったんだ。何故なら、 僕は自分が小説を書けるための日本語を、新しい日本語を、自分の手で作り出さなくてはならなかったからだよ。既にある日本語の文体を借りて小説を書くこと が僕にはできなかったんだ。そういう意味では僕は自分がオリジナルだと思う 。」 [ 村上 1994.]
英語で書くことを断念し、母語の中で、いかに自前の言語でオリジナルに書くか、という作家の意識的な戦略と産みの苦しみが感じられる。
作家の発言はある程度において作家の自己弁護であるから、少し割り引いて耳を傾けなければならないが、彼の作家としてのキャリアのスタートが「文体の新しさ」を起点としていることがこの発言の信憑性を高めている。
こ うした意識的な文体変革を志している作家が旺盛に翻訳を行っていることは決して無視できないことであり、そこに作品との相関関係、共犯関係などを含めた創 作過程の足掛かりがあると推測できる。そうした、広く受容されている村上春樹の文体に関わる創作過程を探求することは、単なる一作家の個性的な創作の軌跡 に還元されるだけでなく、より高次的な意味での日本語表現の可能性に貢献できるだろう。
第 2 節 翻訳における「忠実」対「自由」
伝統的に翻訳論の世界では「忠実」対「自由」という概念がある。翻訳の実務を考慮すればこれは単純な二項対立ではなく、多くのジレンマを抱える複雑な問題である。しかし、翻訳の方針 (strategy) を決定する際には、原文に忠実に訳すのか、あるいは逐語的な訳を超えて目標言語の読者に分かりやすく訳すかという異なるベクトルが決定要因としてある。そしてその狭間でジレンマを抱えつつ葛藤するのが翻訳者という存在である。
こうした翻訳論における「忠実」対「自由」という概念は時系列的に、言語学の変容と呼応するように、姿形を変えて論じられてきた。そして、その傾向は原文への忠実を意識した起点言語志向から目標言語読者を重視した目標言語志向にシフトしてきている。
(3)
「概して言えば、翻訳論の主題の一つは原テキストからの距離と執着性であると言える。 翻訳論は時系列的に原テキスト志向 (source text
oriented) から目標テキスト志向 (target text oriented) へと展開している。
つまり、翻訳者は現場の人々による実際のコミュニケーションにおいてテキストがどのように用いられるかに注意を払わなければならない、ということが強調さ
れるようになったと言える。そしてこの傾向は構造主義からテキスト言語学、語用論、関連性理論へと変遷してきた各時代の言語学の主流と呼応している。」
[Hatim,B.2001. 序文 拙訳 ]
本論は文体論と翻訳論の
接点にあり、その背景には「翻訳とは何か」という問いがある。そしてこの「翻訳とは何か」という問いは地平線の遠く彼方にある蜃気楼を追うがごとく解答の
困難な問いである。この問いは古来より枚挙に暇がない人物たちを饒舌にしてきが、多くの答えがジレンマを抱えているように思われる。しかし、言語学とそれ
にまつわるパラダイムの変遷を考慮すると、原文との忠実性よりも、目標言語内でいかに表現するかという目標言語志向へとシフトしているということである。
そして、このパラダイム・シフトは現実的に「村上春樹訳」の出版に関する状況に色濃く反映されているように思われる。
第 3 節 独立したテクストとしての翻訳
原 文への忠実を重んじる原テクスト志向 (source text oriented) の立場に立てば、翻訳者はできるかぎり透明にならなくてはいけない、存在を主張するべきではい、個性を表に出すべきではない、ただ原作に全面的に奉仕すべ きだ、ということになる。しかし現実には誰が訳すかによって作品の相貌や色合いががらりと変わる。
2003 年に読書界を席巻した話題は、村上春樹訳の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』( J ・ D ・サリンジャー著 白水社 2003 年)の出版であった。旧訳の登場以来 40 年を経て、日本を代表する作家が古典の名作を自ら希望して訳し直したということで話題を呼んだ。その他にも 2003 年には鴻巣友季子訳の『嵐が丘』( E ・ブロンテ著 新潮文庫)や高見浩訳『日はまた昇る』(ヘミングウェイ著 新潮文庫)、中野康司訳『高慢と偏見』(オースティン著 ちくま文庫)などが「新訳」として刊行された。
これらの新訳現象はリフレッシュされた名作に期待をかけるという、マイナス成長を続ける出版界の経済事情から説明が可能であるが、翻訳のあり方を問う翻訳論の立場から考慮すると様々な問題を含んでいる。
まず、時系列で考えると「翻訳の賞味期限」という言語の変容の問題がある。特にここでは日本語という個別言語の変容に関わる問題である。
例えば、 高見訳『日はまた昇る』では、旧訳で「滑稽(こっけい)だよ」となっていた主人公ジェイクの言葉を「笑っちゃうね」と現代風の会話にしている 。『嵐が丘』の旧訳に登場する「ぼくは汚ないのが好きなんだ」とのヒースクリフのせりふは、鴻巣訳では「俺(おれ)はバッチイのが好きなんだよ」となっており、彼の野性味が強調されている。つまり、 歴史的な名訳であっても、使われている言葉は時とともに古びていくという賞味期限の問題である。
そ して次に、ある原作に対して同時に複数の翻訳版があるということは翻訳が単に異なる二テクスト間での情報の置き換え(表記の置き換え)にとどまる作業では ないということを意味する。つまり、もし翻訳が「ある言語( L 1 )によって構成されたテクストを他の言語( L 2 )によって構成される全く等価のテクストに変換すること」と定義されるならば、複数の翻訳版が存在する必要はないのである。すべてのテクストは名札を張り 替えるように、等価な別の言語のテクストに翻訳されるはずである。そして、この二種類のテクストは等しい価値を持つと目される。
しかし、実際にはこの二種類の等価であるはずのテクストはそれぞれお互いの言語の文化的背景を反映し、およそ等価とは言い難い価値と構成を示しているのである。
そして、こうした翻訳の起点と目標の間に差異があるからこそ翻訳者という存在がクローズ・アップされるのである。
翻訳者の個性が意識されるのは「翻訳」という行為に「解釈」と「表現」という主体的な行為が含まれているからである 。 翻訳者は「解釈」において原テクストの意義をつかみ、テクストの意味決定の主体となり、その意味を「表現」において具体的に言語を用いて実現する自由と責 任を持っている。テクストは動的な現象であり、そのテクストを翻訳するという行為も動的な一回限りの主体的行為なのである。
1 .Intralingural Translation (広義の翻訳:言い換え、解釈に関わる部分、図 2 )
2 .Interlingual Translation (狭義の翻訳:言語間の言葉の変換、図 3 )
3 .Intersemiotic Translation (記号間の翻訳:言語以外のメディアを含む翻訳、図 4 )
図 2 . Intralingural Translation |
図 3 . Interlingual Translation |
図 3. |
図 4 . Intersemiotic Translation |
一 般的には、2が狭義の翻訳として本来的な意味の「翻訳」として考えられているが、上述した「解釈」と目標言語内の「表現」を考慮すると、それらの主体的行 為を包含する1の「言語内行為としての翻訳」が複数の翻訳版を生じさせた新訳現象では重視されているように思われる。
例えば、村上春樹訳『キャッチャー・イン・ザ・ライ』刊行を期に行われた「村上春樹訳を読む」という対談 の中で沼野充義は
(4) 「村上さんが新訳を通して、ある意味で本質的な読み直しをしたと言えるのは、たぶん、この物語を [ 無垢な自我対フォニー(いんちきな)な社会 ] という対立の構図に解消するんじゃなくて、むしろ自分の内面に抱えているどうしようもない葛藤を括りだしていく方向で読み解いているからではないか。自己 に本質的に対立するものがあるとすれば、それは社会ではなくて、むしろアルター・エゴみたいな形の聞き手ではないか。 村上さんのこの文体はそういう解釈を引き寄せます 。」
と述べている。旧訳の野崎訳が若い鬱屈した男の子が社会に反抗しているような乱暴な印象を受けるのに対して、村上訳では「何で自分はこうなったのか」とい
う自問が多いと沼野は述べている。これはあくまで沼野の「解釈」であるが、そこには「翻訳者村上春樹」の解釈が不可分であり、村上春樹の新訳における「表
現」の違いが作品解釈の違いを生んだのである。また、同様に村上訳の翻訳チェッカーとして村上と多くの共同作業をしている柴田元幸も以下のように述べてい
る 。
(5) 野崎訳のメインテーマは「大人は判ってくれない」である。たとえば “ People never believe you” といった一節を「 大人 ってのは絶対ひとを信用しないものなんだ」と訳している。<正しい「僕」/間違っている大人たち>という明確な二分法がそこにはある。一方村上訳は、「 人 に信用してもらうってのは、簡単じゃないんだ」となっている。世界との関係の結び方の困難がテーマとなっているわけだ。全体に、村上訳は英語の you をほとんどの場合そのまま「君」と訳していて(これはこれまでの村上訳にもあてはまることだが)「僕」が「君」に語りかけているという色合いが強い。 その点でもやはり、孤立する個、ではなく関係(あるいはその困難)が前面に出ている。
野崎訳では people を子供に対する「大人」として訳しているのに対して、村上訳では一般的な「人」として訳しているということである。そして、この people という英語に対する日本語の表現の違いが作品全体の解釈の違いに大きく影響しているというということである。
も ちろん、翻訳において、「言語間行為としての翻訳」と「言語内行為としての翻訳」は不可分であるが、本論では上述のような「表現」に関わる翻訳の「言語内 行為」に焦点を絞り、翻訳の文体を検証することに主眼を置く。対象となるのは「翻訳家としての村上春樹」とその翻訳活動である。村上春樹はこれまで多くの 翻訳を行ってきた。
第 4 節 翻訳家としての村上春樹
古 来より創作活動と翻訳活動を兼ねる作家は多い。ボードレール、プルースト、 V ・ラルボー、 A ・ジイド、 M ・ユルスナール、 P ・オースター等、日本においても二葉亭四迷、内田魯庵、森鴎外、大岡昇平、小島信夫、金子光晴、渋澤龍彦、池澤夏樹、高橋源一郎等、訳書数の多少を問わな ければ枚挙に遑がない。しかしながら、現代において村上春樹ほどに翻訳を行っている作家は稀有である。
(6) 「僕は現代日本文学史の中でも、翻訳量と E メールの返事を書く量がいちばん多い作家でしょうね。ギネスブックに載ってもいいんじゃないかな(笑)」
と 本人が自嘲気味に翻訳量を誇示しているが、その翻訳量を数字にすると単に本業の片手間で翻訳をこなしている量ではない。彼はこれまでに S ・フィッツェラルド、 J ・アーヴィング、カーヴァーといった代表的な作家を筆頭に現在まで 16 人の作家の長編小説、短編小説、自伝などを含めて計 48 作品を翻訳している。
作家であるのになぜこれほどまでに翻訳を行っているのかというのは、本論の根底にある疑問であるが、まず単純に「翻訳」が好きであるということがその答え としてあるだろう。村上春樹は本業の小説を書くことに関してはあまり饒舌にならないが、翻訳についてはその「楽しさ」をよく表現することが多い、村上は翻 訳の喜びを以下のように語っている。
(7) 「翻訳には、まずテキストを見つける喜びがあり、それをファーストドラフト(草稿)で横を縦にする喜びがあり、それを徹底的にリバイス(校正)する喜びがある。 三段階で三度楽しめる、素晴らしいものなんですよ 。」 [ 村上 1999b.]
(8) 「翻訳というのは僕にとってはとても大きな意味を持つ仕事だし、翻訳作業から多くの大事な物事を学んできた。 奥の深い、喜びに満ちた仕事である 。」 [ 同上 ]
そして、村上の翻訳行為が単に自己充足的な趣味に終わるのではなく、適正に評価され、批評されていることは言うまでもないことである。肯定的なものは、 2003 年読書界を席巻した『キャッチャー・イン・ザ・ライ』の新訳(村上春樹訳)問題などであり、否定的な批評の代表としては千石英世の以下のような評論であ る。千石は原文のレイモンド・カーヴァ-の作品がもつ労働者階級のダーティーなイメージが村上春樹訳では洒脱な世界に変わっていることを指摘する。以下に その抜粋を引用する。
(9) 「ヴィタミン剤の飛び込みセールスの販売員になって、やがて班長にまで昇進した妻のことを、夫は、「…やがて、彼女は自分のチームを組んでビルの中に小さ なオフィスを持つまでになった。しかしチームのメンバーの女の子はしょっちゅう入れ替わっていた。…でも、中には働きの良い子もいた。彼女たちはちゃんと ヴィタミンを売ることができた」と語る。傍点を付した部分、殊に引用末尾は、 原文の泥臭さに比して、出来上がった日本語は洒脱に過ぎるだろう 。 だが、それは訳者の意図もあるかもしれぬけれど、多分、翻訳文化の持つ風俗的宿命であり、それはむしろ翻訳の意義ですらあるもかもしれない。 」 [ 千石英世 1989.]
千石は最終的に「翻訳の宿命」、あるいは「翻訳の意義」として 村上訳の個性をまとめているが、その良し悪しはともかく、原文の内容や物語の展開と関連して村上春樹の翻訳が問題となっているのである。そして前述のとお り、村上春樹自身もその行為に意義を見出し、翻訳という行為に問題意識を持っているのである。
極端に言えば、翻訳とい う行為が何らかの問題となるのは常に言語の問題であり、翻訳を行うことは少なからず言語に自覚的になるということである。翻訳という行為は決して辞書引き や単純な単語の置き換えではない。翻訳者は外国語の規範とぶつかりあいながら、対応する母語を操作し、「選択」するという意味で母語に対して批判的であ り、距離を置いて母語と向き合っている存在といえる。ヤコブソンの言う「言語科学の不断の精査」 を行いながら、母語を「選択」するのが翻訳の過程である。この過程があるからこそ、千石は村上春樹訳が原文とは異なる洒脱さを持つ点を批判しつつも「翻訳の宿命」と述べたのである。
このように複雑な「翻訳」という営為を繰り返してきた「翻訳者」作家である村上春樹にとって、翻訳と小説に対する態度には職業的な差異がないように思われる。村上は翻訳と小説の関係について以下のように述べている。
(10) 「あっちの世界のものごとをこっちの世界に移し変えるというのが、僕の考えでいうと文章を書くということなので、それは翻訳でも小説でもそうなんです。 翻訳の場合はテキストがあって、それをこっちの言葉に置き換えるわけですね。小説の場合はそうじゃなくて、一種の違うフェイズのなかにある、自分のものの 感じ方、考え方というものがあって、それは非常に何て言うか、現実的ではない、具体的ではないわけです。 それを文章の形にする、つまりこっちの世界に移し変えるというのは、トランスレートするということなんですね。そういう意味で 翻訳と小説は原理的に同じ作業であるわけです 。だから僕はそういうふうに感じているから、翻訳というものに対して、小説を書くのと同じような意識で入っていけるんじゃないかなというふうには思う。」 (村上春樹特別インタヴュー「僕が翻訳をはじめる場所」『翻訳の世界』 1989 年 3 月号より)
言わば一般的な翻訳という行為がまずあり、その疑似体験として「あっちの世界」を擬似的に「翻訳」することが村上春樹にとっての「小説を書く」という行為だということである。また、この疑似体験に関して、以下のように述べている。
(11) 「僕はある意味では何かを疑似体験するために小説を書くんです。英語に「俺の靴に足を入れてみろ」という表現があって、これは「俺の身にもなってみろよ」という意味なんだけれど、 小説を書くというのは誰かの靴に足を入れてみる作業 でもあるんです。」 ( 「村上春樹に対する 18の質問」『広告批評』1993年2月号)
この「誰かの靴に足を入れてみる」という言い回しは翻訳に関するインタヴューでも発せられている。
(12) 「(翻訳の際に男性作家の作品と女性作家の作品に違いはあるかという問いに対して)関係ない。英語で言う「 相手の靴に足を突っ込める 」かどうか、です。」
[ 村上 1999b.]
つまり、村上流の言い方をすれば、小説を書くことも翻訳をすることも同様に「誰かの靴に足を入れてみる」という行為なのである。
作家の翻訳の最大の特徴は、何よりも作品を「選択」できる、ということにある。作家の翻訳行為は大抵の場合、頼まれ仕事ではないので恣意的に作品を取捨選択できるという点に特徴がある。
(13) 「翻訳をやってれば時間がもつし勉強にもなるし、それに飽きたらまた自分の書きたいものを書けばいいし、そういう意味では翻訳は続けていきたいと思う。日本の翻訳というのは有名なものしか訳さないところがあるから、 自分の好きなものを訳して紹介できるのは楽しいし、それにメッセージを託すことができるしね。 」
( 「 対談 仕事の現場から 中上健次×村上春樹」 『国文学』 1985.3 )
つまり、自らの作品の世界観を補足するもの、あるいは自らの作品と近いものを作家の嗅覚で嗅ぎ分け、自ら母語に翻訳するということである。村上は言う、
(14) 「翻訳には相性があるんです。僕は訳すときに、何度も「本当に自分がこの人を訳していいんだろうか」と考えますが、それは どこまでコミットできるか 、自分が寄り添えるかということなんです。女の人と付き合うのに似てますね。ちょっといいな、と思って付き合うのではなく、やっぱりどこまで責任もてる か。ただ、あまり考え過ぎると何にもできなくなってしまうから、その辺の見極めが難しいですけど。」 [ 村上 1999b.]
自らの世界観と相性が合い、その世界にコミットができて、ある程度の責任 が持てるかどうかということが作品の選択要因としてある。そしてそのようにして選ばれた作品を母語に変換するのである。その意味で村上春樹の「翻訳」に小 説とのリンクがあるとすれば、彼の「翻訳」と小説の間に本質的な差異はないということになる。つまり、「翻訳家としての村上春樹」の文体を検証すること は、いずれ「作家としての村上春樹」の文体への説明へとつながるということである。両者の間には少なからず文体形成において共犯関係があるのではないだろ うか。そして、この点が「作家であるのになぜこれほどまでに翻訳を行っているのか」という問いに対して本論が最終的に提示したい答えである。
第 5 節 文体形成のヴィークルとしての翻訳
「翻訳家としての村上春樹」が最初に世に出たのは 1980 年、 31 歳のとき の ことであった。このときまで彼は外国に出たこともなく、英語圏に長期間滞在したこともなかった。にも関わらず、英語で書かれた作品を翻訳したということ は、彼の英語との付き合いに特別なものがあったと考えられる。以下では、特に翻訳との関係を重視しながら彼の英語との付き合いを述べる。
まず、大学受験を控えた高校 2 年生のときに受験教材の副読本でトルーマン・カポーティの『無頭の鷹』 (“Headless Hawk” Capote, Truman) と出会い、その文章に感動した ことが彼の英語圏の小説との付き合いの発端であるとされている。そして、それを何度も反芻し、自発的に英文和訳を行っていた ということである。さらに、神戸の古本屋で英語圏の小説を買い漁り、受験勉強とは関係なく、様々なペーペーバックを読んでいた。
さらに、大学に入り、特に英語の成績は特に良かったわけではないものの「趣味のように」翻訳を行っていた という。そして作家としてデビューするまで JAZZ 喫茶のマスターをしていた時代にも、趣味で多くの英米小説を読んでいたそうである。そして、原典を直接読んでいたために、 SF 小説などの知識は素人のレベルを超えていた ということである。
端的に彼の英語との関係を述べたが、少なからず作家としての文学的ルーツに英語で書かれた小説というものが影響していたと考えられる。
特に英語圏の作家レイモンド・チャンドラーや、カート・ヴォネガットの影響が村上春樹の初期の作品にあると指摘されることが多いが、そのことについて本人は以下のように述べている、
(15) 「(チャンドラーとの類縁性について)確かに僕は文体のレヴェルにおいてはチャンドラーに多くを負っている。これを(『羊をめぐる冒険』)書いたのはもう 十年くらい前のことだから、それから僕はもう随分変化しちゃったわけだけれど、でも僕はとにかくそのときには、 物語を語るためのヴィークル(乗り物・手段)として彼の文体を必要とした んだね。でもね、チャンドラーの文体を 日本語に組み換える っていうのはそんなに簡単なことじゃないんだよ。そもそも英語を作り上げている文化的概念と、日本語を作り上げている文化的概念とは、それこそまったく 違ったものだからね。でもとにかくそれが僕の試みたことなんだ。 言語の組み換えによる概念の転換 。
僕を含んだ日本の若手作家たちが今やろうとしているのは、多かれ少なかれ 、新しい日本語の文体を築き上げることだと思うんだ。 もし君が何か新しいことを語ろうとするなら、君は新しい言語を必要とする。そうだろう?」
[ 村上 1994.]
物語を語るためにの媒体 (vehicle) として、チャンドラーの文体を借りたということである。
そして、それによって築き上げられた文体は「異化作用」を持ち、新しい文体として成立するはずだという作家の戦略である。さらに村上は言う、
(16) 「僕らの多くは今、日本語を再構築しようとしている段階に入っているのではないか。三島が用いていたような言語的美しさ、精妙さ、それは確かにけっこうな ことだ。でもそれが通用し機能していた時代は過去のものとなっている。我々はもっとあたらしい試みに向かわなくてはならない。我々がやらなくてはならない のは、 言語的バリヤーを越えて、より広い世界に語りかけることだ。そのためにはある種の言語的組み換えが必要なんだ。既成の文学言語ではなくて、自前の言葉が必 要なんだ。 もちろん我々のやらなくてはならないのは、それだけではない。しかし、そういう試みや姿勢は我々に新しい視点を与えてくれるはずではないだろうか。」
[ 同上 ]
やや抽象的ではあるが、より広い世界に語るためのヴィークルは既成のものではだめだという文体への変革意識が表れている。そして、「言語的バリアー」や「言語的組み換え」という箇所に「翻訳家としての村上春樹」が垣間見られる。
英語の文体に形を借りて、それを日本語に組み換える、ということはより単純に言えば一般的に翻訳が内包している行為のことである。すなわち、村上春樹にとって「翻訳」という行為にも文体形成のヴィークルとしての作用があるのではないだろうか。
そして、この「文体形成のヴィークルとしての翻訳」というのが本論で中心的に検証する問題である。例えば、村上の以下のような発言は同時代にバイリンガル作家として活躍する多和田葉子 やリービ英雄 の問題意識と呼応する。村上は言う、
(17) 「日本人だから日本語はほっといてもまあ一応は書けるわけだけど、ほっといても書ける文章というのはかえって小説になりにくいと思うんです。 自己をうまく表現するためには何かの形を借りる必要がある 。」(小説新潮 1985 年夏 臨時増刊号 村上春樹ロングインタヴューより)
(18) 「日本語というものにはいろんなものが染み付いているから、例えば自分がこれまで生きてきた生活感覚のようなものとかが、それをなんとか排除したかった。」
(村上春樹特別インタヴュー「僕が翻訳をはじめる場所」『翻訳の世界』 1989 年 3 月号より)
自己に染み付いたものによって書く文章というのは小説になりにくく、小説としてうまく自己を表現するためには「何かの形を借りる必要がある」ということで ある。そして、この「何かの形」というのが村上春樹にとっては、英語の文体であり、「翻訳」という言語の組み換え行為なのである。
同様に、ハンブルグに在住しドイツ語と日本語の両方で創作を行う現役のバイリンガル作家多和田葉子は以下のように言う、
(20) 「たとえば、まずドイツ語で考えてから日本語で書き始めると、跳躍できる大きさが違うというか…。 つまり日本語には、ダラダラグダグダと書いてしまう危険性もあるけれども、ドイツ語は、今自分がいる地点から思い切りジャンプしないと文章がかけないよう なところがあるのです 。」
(21) 「(言葉と自由について)言葉にはちょうど「検閲官」のようないやな面もあるのです。(中略)誰が聞いても美しく聞こえる日本語であったら、かかれてい ることは、今みんなが考えて正しいと思っていること、社会が私たちに正しいと思わせているようなことを繰り返したに過ぎないからです。」
(22) 「 小説を書くというのは、言葉を垂れ流しにすることの逆で、普通言葉を使っている時にはない何らかの緊張感を、自分と言葉との間にそして自分自身に対しても演出すること 。そういった過程を経ないと、小説は生まれて来ないと思うのです。その緊張感をいかにして演出するか。もちろん外国に住まなくてもいい。 その人なりに演出の仕方があるでしょう 。」
[ 多和田 1999.]
多 和田葉子にとってはまさにドイツ語という存在が「文体形成のヴィークル」であり、自らの文体を演出する媒体であったのである。特に多和田の「 小説を書くというのは、言葉を垂れ流しにすることの逆で、普通言葉を使っている時にはない何らかの緊張感を、自分と言葉との間にそして自分自身に対しても 演出すること 」という箇所は村上の発言「 ほっといても書ける文章というのはかえって小説になりにくいと思うんです 」とほとんど同じことを意味している。そして、多和田が最後に言った「その人なりの演出の仕方」というのが村上春樹にとって「翻訳」だったのではないだろ うか。基本的に多和田葉子も村上春樹も「小説を書く」ということに対しての問題意識は変わらない。ただ、文体形成のためのヴィークル(媒体)が違うだけで ある。
そして、「翻訳」をヴィークルとして新しい文体を形成してきた村上春樹の作品が第一節で述べたように広く受容されているということは、日本語の変化にも関係があるのではないだろうか。
以上、本章では村上春樹の発言を中心に、特に翻訳に関する問題意識を述べた。主な要点をまとめると以下のようになる。
• 村上作品は現代において広く受容されている
• 村上春樹は文体に自覚的な作家である
• 村上春樹にとって翻訳と小説に対する問題意識に差はなく、共通項の多い相互補完的な関係である
『 CD-ROM 版 村上朝日堂』 朝日新聞社 2001 より。
Japan.P.E.N.Club 1997. Japanese Literature in Foreign Language1945-1995 .Tokyo: Japan Publisher Association
ドイツに関しては、シュタルフ 1995:104-108 、フランスに関しては野崎 2001: 115-118 を参照。
「 物語は新しいものではない。どこにでもありそうな話である。にもかかわらず新鮮な印象を受けるのは 、 文体が新しいからである 。文体のこの新しさは、人間とその世界に対する「僕」の姿勢の新しさによっている。「僕」は他者に内的に関わろうともしない。遠くを見るような眼で現在を見、友人を見ている。」 三浦雅士 1981.
村上春樹 1990. 「台所のテーブルから生まれた小説」『村上春樹全作品 1979 - 1989 ①』講談社
2003 年 9 月 7 日 日本経済新聞 朝刊 :p.23 「名作に現代の香り、海外文学、新訳で読者開拓(活字の海で)」より
「二つの言語の比較はいずれも、それらの相互の翻訳可能性についての検討を含む。したがって、広く行われている言語間の伝達、
とくに翻訳活動は、言語科学による不断の精査を受けなければならない 。」
ヤコブソン 1973. 「翻訳の言語学的側面について」『一般言語学講義』みすず書房
『 Happy End 通信』 1980 年 3 月号にてフィッツジェラルドの
”Three Hours between Planes” を訳す。日本語タイトルは「失われた三時間」。
「大
学受験用の副読本で、「ヘッドレス・ホーク(無頭の鷹)」の冒頭の文章が出ていたんです。僕は英語の成績はあまりよくなかったんだけど、英文和訳するのは
昔から好きで、テキストを片っ端から買ってきて一人で訳してたりしてたんですね。そのうちの一冊にカポーティの「ヘッドレス・ホーク」が載っているのが
あって、それを読んで感心して、好きになった。」
(小説新潮 1985 年夏 臨時増刊号 村上春樹ロングインタヴューより)
「実は僕は高校時代に、カポーティの ”The Headless Hawk” というのがありますね、あれがすごく好きで、自分で受験勉強のために訳したことがあるんです。」
(中田耕治×村上春樹 対談「翻訳に「個性」の時代到来」『翻訳の世界』 1985 年 3 月号)
「英文和訳をやらせたら、朝から晩までやっているという変な高校生で、受験勉強もひたすら英文和訳だけ(笑)」 [ 村上 1999b.]
大学卒業して店をやり始めてからもちょっとずつ続けてました。といっても、とくに翻訳家になりたいわけではなく、英文和訳の延長みたいな感じで、ただ好きなように右から左に置き換えていただけですけど。 [ 同上 ]
*多和田葉子氏略歴
1960 年生 1982 年早稲田大学第一文学部露文科卒業。同年よりドイツ・ハンブルグに
在住。 1987 年より執筆活動を開始。 1988 年ドイツ語で執筆開始。 1990 年ハンブルク大
学修士課程修了。ハンブルク市文学奨励賞受賞。 1991 年『かかとをなくして』で群像
新人賞を受賞。 1993 年『犬婿入り』で芥川賞受賞。 1999 年マサチューセッツ工科大学
よりドイツ語の作家として招かれる。 2000 年チューリッヒ大学博士課程修了(ドイツ
文学)。泉鏡花賞受賞。ハンブルク在住。
「(中上健次らの現代日本文学の作品を英訳をすることについて)結果が自由訳であっても、無理して移そうとして努力しますから、 その無理の中で文体がより克明になるということがあるんですね。これは日本語の創造に直接繋がると思います 。読むことが書くための一番の勉強になるんですから。」
(インタヴュー 「日本語で書く根拠 外側から獲得した日本語」リービ英雄 )