1.�@�͂��߂�
1.1�@ �w�Z�ɂ�����IT�C���t���̌���
����15�N�x�����w�Z�ɂ�������̎��Ԓ����i�����Ȋw��2003�j�ɂ��ƁA���݁A���w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�ɂ�����A�C���^�[�l�b�g�ڑ����́A���w�Z��99.7���A���w�Z��99.9���A�����w�Z�ł�100���ƂȂ��Ă���B�܂��A�C���^�[�l�b�g�ɐڑ����Ă��鋳��p�ɂȂ��Ă���B�i�����Ȋw��2004�j
�� Rihoko Inoue*
:The streaming content delivery and the utilization model in the
elementary and primary education
*Graduate School of
Media and Governance, Keio University, 5322 Endou Fujisawa-shi, Kanagawa,
252-0816 Japan
�R���s���[�^�̊����́A���ꂼ��A91���A93���A82��
�ł���B�R���s���[�^�����ɂ����ẮA�R���s���[�^�����ς݂̋����́A99.1���A���̂���LAN�ڑ������Ă��鋳���́A94.8���ł���B�������A���̑��̋����ł́A�R���s���[�^�����ς݂̋�����2�����x�ALAN�ڑ������Ă��鋳���̊����͂���ɏ��Ȃ��Ȃ�B����́A�R���s���[�^�����ȊO�̕��ʋ����ȂǂɃR���s���[�^�y���A�܂��A�C���^�[�l�b�g�ڑ����s���Ă�������
1.2 ����p�f�W�^���R���e���c
�C���t�����������i����Ă����ɂ����āA���ނȂǂ̋���p�f�W�^���R���e���c�̕��y�Ɨ��p�̒x�ꂪ�ڗ����Ă���B����p�f�W�^���R���e���c�̕��y�Ɨ��p�́A����̓��e�E���@�Ȃǂƒ��ڊW������A�܂��A�f�W�^���R���e���c�͒��쌠�ŕی삳��Ă���̂ŁA���G�Ȍ����W�����݂��邱�ƂȂǂ����̗v���ł���B
�f�W�^���R���e���c�̒�`�́A�l�X�ł���B����ɂ�����u�R���e���c�v�Ƃ́A�u�w�K�̑ΏۂƂȂ���̂̏W���v�ł���ACAI�iComputer Assisted Instruction�j�ł́A�������w�K�\�t�g�E�F�A�ƌĂ�ł����B�i�{��2004�j�\�t�g�E�F�A�́A�u�v���O�����i�R�[�h�j�v�̕����Ɓu���e���v�i�f�[�^�j�̂ǂ�����܂ށB�������A�}���`���f�B�A���p�ɂ��A�u���e���v�i�f�[�^�j�̔�d���������A���̕������u�f�W�^���R���e���c�\�t�g�E�F�A�v�ƌĂсA���ɍŋ߂ł́u�w�K�I�u�W�F�N�g�v�iLearning Object�FLO�j�ƌĂ�ł���B�i�{��2004�j�{�����ł́A�f�W�^���R���e���c�Ɗw�K�I�u�W�F�N�g�`�Ƃ��Ĉ����B�w�K�I�u�W�F�N�g�́A�L�`�ł́u�R���s���[�^��C���^�[�l�b�g�����p��������ɂ����ė��p�����A������f�W�^���A��f�W�^���f�ށv�i����U�����Ƌ���ق�2001�j�Ƃ���邪�A�{�e�ł́A�f�W�^���f�ނ����������B�w�Z���ŗ��p����鋳��p�f�W�^���R���e���c�ɂ͗l�X�ȕ��ނ̎d�������邪�A���ʋ����ɃR���s���[�^�ƃC���^�[�l�b�g�ڑ������y���Ă������Ƃ��l������ƁA�l�b�g���[�N�ڑ��̗L���ŕ��ނ����邱�Ƃ��A����p�f�W�^���R���e���c�̕��y�Ɨ��p�ɂ��čl����ꍇ�ɗL�v�ł���ƍl����B
����p�f�W�^���R���e���c���Ȃ킿�A�w�K�I�u�W�F�N�g��{�����ł́A2��ނɕ�����B
�P�j �l�b�g���[�N�ڑ��̕K�v���̂Ȃ��A��l�b�g���[�N�^�w�K�I�u�W�F�N�g
�Q�j �l�b�g���[�N�ڑ��̕K�v���̂���A�l�b�g���[�N�^�w�K�I�u�W�F�N�g
����ɁA�P�j�̊w�K�I�u�W�F�N�g�́A�w�K�I�u�W�F�N�g�ƃv���O�����Ȃǂ��p�b�P�[�W������Ă��ė��p������̂Ƃ���Ă��Ȃ����̂ɕ�������B�܂��A�l�b�g���[�N����_�E�����[�h���邱�Ƃ̂ł���w�K�I�u�W�F�N�g�Ȃǂ��A�_�E�����[�h��́A�l�b�g���[�N�ɐڑ�����K�v�����Ȃ��Ȃ�̂łP�j�Ɋ܂܂�A�����͊w�K�I�u�W�F�N�g�������_�E�����[�h����ꍇ�ƁA�v���O�����Ȃǂ��ꏏ�Ƀ_�E�����[�h����ꍇ���l������B
�Q�j�̃l�b�g���[�N�^�w�K�I�u�W�F�N�g�ɂ����ẮAWBT�Ȃǂ̏ꍇ�A�w�K�҂��u���E�U����āA���̃V�X�e����Ŋw�K�I�u�W�F�N�g�𗘗p����B����A�X�g���[�~���O�R���e���c�̊w�K�I�u�W�F�N�g�i�X�g���[�~���O�w�K�I�u�W�F�N�g�j�𗘗p����ꍇ�́A�w�K�I�u�W�F�N�g�ł���z�M����Ă���f�[�^���w�K�҂��R���s���[�^��ŃX�g���[�~���O�R���e���c�v���[���[�Ȃǂ���ė��p����B�܂��AWeb�y�[�W�Ȃǂ��{������ꍇ�́A�_�E�����[�h����i�������R���s���[�^�Ɏc��j���Ƃ��\�ł��邪�A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A���p�҂͉{������݂̂Ȃ̂ŁA���p�҂̃R���s���[�^�ɂ̓L���b�V�������c�炸�A�l�b�g���[�N�ɐڑ����Ȃ���Ίw�K�I�u�W�F�N�g�𗘗p�ł��Ȃ��B
���݂́A�w�K�I�u�W�F�N�g�́A���⎩���̂Ȃǂ̌��I�@�ւ��J�����Ă�����̂������ANICER�i������i�V���i���Z���^�[�j�́A���ɏ�������I�@�ւƂ��ċ���p�f�W�^���R���e���c�i���̏ꍇ�́A������w�K�\�t�g�E�F�A�ɋ߂��T�O�́A�f�[�^�ƃv���O��������̉����ꂽ���̂��܂ށj�̏��݂��Љ�Ă���T�C�g���J�݂��Ă���B�����̃f�W�^���R���e���c�ɂ��ẮALOM�iLearning Object Metadata�j���o�^����Ă���A�������\�ł���B�������A�L���f�W�^���R���e���c�ɂ��Ă̏Љ�f�[�^�͂Ȃ��B�܂��A�l�X�Ȑl���A���Ȃ̃f�W�^���R���e���c�����痘�p�̂��߂ɖ����Œ��A���̃R���e���c�����Ƃ�w�K�ŗ��p�ł��邱�Ƃ��\�Ȏd�g�݂��\�z�����T�C�g�͑��݂��邪�A�p�������Ȃ��A�ꕔ�̃R�~���j�e�B�Ɍ����A�ꎞ�I�Ȃ��̂őr�����Ă�����̂��قƂ�ǂł���B�iJAPET�ue-Japan�\�z�U�v�����ψ���2004�j
1.3 �{�����̖ړI
�{�����ł́A�X�g���[�~���O�w�K�I�u�W�F�N�g��������������ɂ����Ĕz�M�E���p���邽�߂̔ėp���f������������B���̂��߁A�����̃f�W�^���R���e���c�̔z�M�E���p�V�X�e������B������Ă��鍀�ڂ𒊏o���A�����̍��ڂ������v���𖾂炩�ɂ���B����ɁA�X�g���[�~���O�w�K�I�u�W�F�N�g���A���̃l�b�g���[�N�^�w�K�I�u�W�F�N�g�Ɣ�ׂĒ��쌠�@�㈵���₷���_���l�����A�����ҁA���p�҂̗��v�o�����X�����A����ɃR���e���c���ʂ̑��i�������܂��V�X�e���Ƃ��邽�߂̍��ڂ��������A���f�����\�z����B���̂����ŁA���炩�ɂ��ꂽ���f���Ɋւ��āA���쌠�@�̊ϓ_����̍l�@���s���B
2.�@�X�g���[�~���O�R���e���c�̓���
2.1 �X�g���[�~���O�R���e���c�Ɣ�l�b�g���[�N�^����R���e���c
�X�g���[�~���O�R���e���c�́A�ʏ�̓���R���e���c�Ɣ�ׂāA�l�b�g���[�N�ڑ����s���_�ɓ���������B��l�b�g���[�N�^����R���e���c�ɂ��ẮA�������k�̊w�т̌���Ɋ�^���邱�Ƃ�������Ă���B�������i2004�j�́A���w�Z5�N���Ȃɂ����āA�w�K�w���v�̂́u�n�ʂ𗬂�鐅���̗l�q���ώ@���A����鐅�̑�����ʂɂ�铭���̈Ⴂ�ׁA����鐅�̂͂��炫�Ɠy�n�̕ω��̊W�ɂ��Ă̍l�������悤�ɂ���v�̋L�q�Ɋւ�����Ǝ��H���s���A���̒��œ���R���e���c�𗘗p���Ă���B�o�����̉͐�◬���E���[�̃f�[�^�A�܂��A�������Ă������⌸�����čs�����̕����オ�鍻��}���ʼn���������̗l�q�Ɋւ���A15�b����30�b�̓���R���e���c���A3�x�J��Ԃ��R���s���[�^�ɂȂ������r�f�I�v���W�F�N�^�ɂ����čĐ����Ă���B�u�������m�F�����������̗����ƁA�i�K�ɂ���Ď��ۂ��قȂ�p�x���瑨���������i��ł���v���Ƃ�������Ă���B�܂��A���l�ɁA�g�x���i2004�j���A���ӂ���̊ώ@�ł͔F���ł��Ȃ����_�ő����������̉f����g�ݍ��킹���W���V�X�e���ɂ����āA���������ۂ�R���e���c�ɂ���Ă�蒼�ړI�ɑ����₷���������Ƃ������Ă���B
�������A�����̓���R���e���c���p�ɂ����ẮA���ƒ��₻�̓W���ɂ����āA����ꂽ���ԁA����ꂽ�ꏊ�ɂ����Ă����{���ł��A�܂����������Ԃ�ꏊ�ɂƂ��ꂸ���R�ɗ��p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�܂��A�����̍쐬����������A���t�̊Ԃŗ��p���������Ƃ��A���ލ쐬�̎��ԓI�o�ϓI�R�X�g���팸���邱�ƂɂȂ邪�A���t�̊Ԃ̑��ݗ��p��O��Ƃ��Ă��Ȃ��B����R���e���c���l�b�g���[�N�^�z�M��O��ɂ���A�����͎��ԓI�ꏊ�I�Ɏ��R�ɗ��p�ł��A�܂��A���t�̑��ݗ��p���\�ł���B����ɂ����́A�X�̎������Ƃ����ɂƂǂ܂�Ȃ��ėp��������A��l�b�g���[�N�^�̓���R���e���c�Ɣ�r���āA�X�g���[�~���O�R���e���c�̗L�p���͖��炩�ł���B
�X�g���[�~���O�z�M�́A��������܂��͊�Ɠ�����Ȃǂɂ����āA�����҂��s�����Ƃ��ʊw�K�����ɂ܂邲�ƍs���Ă���ꍇ���قƂ�ǂł���B�������A�X�g���[�~���O�w�K�I�u�W�F�N�g�́A�������炾���ł͂Ȃ��A������������ɂ����ė��p�̉\���������Ƃ�����B
������������̌���́A�\�Z�̊W�ȂǂŁA���쌠�҂��o�ϓI���v���咣����悤�ȗL���R���e���c�̗��p��A����҂����p�ɂ��ď��������肷��ꍇ�Ȃǂɂ����āA���p���邱�Ƃ�����ȏɂ���B����A�f�W�^���R���e���c�̒��쌠�҂́A�L���R���e���c�̗��p�̕��y�����Ă��钆�A�o�ϓI���v�⌠����ی삵�Ȃ�����A�f�W�^���R���e���c�����ʂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����͍����Ă���Ƃ���ł���B
2.2 �X�g���[�~���O�R���e���c�̒��쌠�@��̓���
�X�g���[�~���O�R���e���c�����앨�ƔF�߂���ꍇ�A���悻���O�ɑ��đ��M����ꍇ�A���M�ҁi�A�b�v���[�h����ҁj�͌��O���M����L���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���O���M���́A�����y�їL���A�܂��A�����`�ԋy�уI���E�f�}���h�`�Ԃ̑S�Ă�������̂ł���A���悻���O�ɑ��Ē��앨�𑗐M����ꍇ�ɓ��������ł���B�܂��A�C���^�[�l�b�g�̂悤�Ȏ������O���M�i���O���M�̂����A���O����̋��߂ɉ��������I�ɍs�����́i�������͗L�������͏����j�j�ɂ�����ꍇ�́A���M�\�����i���앨���������O���M�����錠���j�������҂͗L���邱�ƂƂȂ�A���M�҂́A�����҂̋����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�X�g���[�~���O�́A�������O���M���s�������ł��邪�A�_�E�����[�h�i�L���b�V�����܂߁j����M�҂ɋ����悤�ȑ��M�̏ꍇ�́A�L���b�V���╡��������M�҂̃p�\�R���Ɏc�����ƂƂȂ�B���{�ɂ����ẮAWeb�y�[�W���{������ۂȂǂ̈ꎞ�I�Ȓ~�ς��u�����v�ɊY�����邩�ɂ��ẮA���炩�ł͂Ȃ��B�ꕔ�ł́A�ꎞ�I�~�ς͕����Ƃ݂͂Ȃ��Ȃ��Ƃ̐������邪�A���I�ɂ͋c�_����Ă��Ȃ��B�i���2002�j����āA�X�g���[�~���O�́A�������O���M�ɂ�����A�_�E�����[�h�́A�������O���M�ƕ����ɂ�����ƌ����A�Ⴂ������ƍl���邱�Ƃ��\�ł���i���2005�j���ہA�č��ł́A�X�g���[�~���O�R���e���c���{������s�ׂ́Aperformance �Adisplay�ƌĂ�A�����Ƃ͒��쌠�@���ʂ���Ă���B�܂��A�č����쌠�@�̋���ړI���p�Ɋւ���TEACH ACT�iTechnology, Education and Copyright Harmonization Act�j�ɂ����ẮA����ړI�Œ��앨�𗘗p����ꍇ�̒��쌠�����ɂ��āA���̔z�M�ɂ����ẮA���Ƃ̊J�u���ԂɃX�g���[�~���O�z�M����ꍇ�݂̂Ɋւ��Č����҂ɖ������Ŕz�M���邱�Ƃ�F�߂Ă���B�X�g���[�~���O�R���e���c�̕ی���_�E�����[�h����ꍇ���ɂ߂��`�ł���B�č��̒��쌠�@�Ɠ��{�̒��쌠�@�͈قȂ�A��T�ɕč��Ɠ��l�ɂ���Ηǂ��Ƃ͌����Ȃ����A���{�̒��쌠�@��ŁA�X�g���[�~���O�ƃ_�E�����[�h�̈Ⴂ���l������\�����l������ƁA���Ȃ��Ƃ��_��Ȃǂɂ����ăX�g���[�~���O�ƃ_�E�����[�h�ɈႢ��݂��邱�Ƃ́A���{�̒��쌠�@�ɒ�G���Ȃ��Ƃ�����B���̂��Ƃ́A���쌠�@��A�X�g���[�~���O�R���e���c�ƃ_�E�����[�h�R���e���c�̈قȂ��Ĉ�����\��������A���쌠�ҁA���p�җ��҂ɂƂ��ė��v������A���̏�A�R���e���c���ʂ̑��i�ɋ����闘�v�o�����X�̂Ƃꂽ�_�쐬�ł���\�������邱�Ƃ������Ă���B
3�D�@������������ɂ�����X�g���[�~���O�R���e���c�z�M�E���p���f��
���݁A�X�g���[�~���O�R���e���c�́A��������ɂ����ču�`���܂邲�Ɣz�M���āA�w�K�҂��ʊw�K���邽�߂ɗ��p����Ă��邱�Ƃ������B���̏ꍇ�A�X�g���[�~���O�R���e���c�́A������̎��Ԃ̒��������w�K�I�u�W�F�N�g�ƂȂ�B
�������A������������ɂ����ẮA���Ǝ��Ԃ̒Z����k�����̏W���͂Ȃǂ��l����ƁA�����Z���P�ʂ̃X�g���[�~���O�R���e���c���L���ł���ƍl����B�������i2004�j�ł́A�����Z���P�ʂ̓���f���́A�J��Ԃ��������A����ɂ�藝�����[�܂邱�Ƃ�������Ă���B����ɁA�������i2004�j���A�u�f���N���b�v�̎����́A���͂�Î~��ł͂킩��Â炢�A���ۂɂ��Ċw�K����ɂ͗L���ł���v�Əq�ׂ�B�܂��A�T�䑼�i2003�j�́A���Ƃɂ����ċ��t������R���e���c�𗘗p����ꍇ�́A�w���̂˂炢�ɂ����āA�Z���P�ʂőI�����s�����Ƃ��w�E���Ă���A�Z���P�ʂ̃X�g���[�~���O�R���e���c�́A�L�v�ł���Ƃ�����B
�����ŁA�{�e�ł́A������������ɂ�����A�����Z���P�ʂ̃X�g���[�~���O�R���e���c���u�w�K�I�u�W�F�N�g���W���[���v�ƌĂсA�����̔z�M�E���p���f�����l����B
3.1 ��s�����ɂ����ĒB������Ă��鍀�ڂ̌���
�����̃f�W�^���R���e���c�z�M�E���p�V�X�e���Ɍ��y���āA���ݒB������Ă��鍀�ڂ𒊏o����B
Nicer��1)�́A���{�ɂ����邠���鋳������������j�I��Web�T�C�g�ł���B��ɁA������������p�w�K�I�u�W�F�N�g���o�^���Ă���ALOM��t�^���邱�Ƃɂ���āA���p�҂����������邱�Ƃ��\�ł���B�i����2002�jLOM�̕��ނ́A�V�w�K�w���v�̂Ɋ�Â��Ă��邽�߁A���ۂ̊w�K�p��Ō����ł���B2005�N2���̎��_�ɂ����āA142607�̊w�K�I�u�W�F�N�g���o�^����Ă���B�w�K�I�u�W�F�N�g�Ɋւ���LOM�ɂ��Ăׂ͍����K�肳��Ă���AIEEE�̕W���ȊO�ɂ�NICER�ŕt�����������̂�����B�w�Z�̌���ł̎g�p���z�肳��Ă���w�K�I�u�W�F�N�g�������f�ڂ���Ă���B����ɁANicer�ł́A�P�P�̊w�K�I�u�W�F�N�g�ɑ��āA���ȏ��̖ڎ��ɑ������L�[���[�h�����A���p�҂̑����i���w���A���w���A���t�Ȃǂ̑����j�ɉ����������Ȃǂ��p�ӂ���A���p���₷���Ȃ��Ă���BLOM�ɂ��L�[���[�h������A�����ɉ��������p�҂̎g���₷�����l�������������B������Ă���Ƃ����悤�BLOM�ɂ́A�����҂�g�p�������L�ڂ���Ă��āA����҂̌����ɔz�������Ă���B
���p�ł́AMPEG�@Archive Station��2�j������B����́AKDDI���J���������AMPEG���Y��1��̃T�[�o�[�ŊȒP�ɓo�^�A�����A�z�M�A�ҏW�A�Ǘ����邱�Ƃ��ł���MPEG�f�[�^�x�[�X �V�X�e���ł���B�P��̃T�[�o�[�ɏW������MPEG�f���Ȃǂ�o�^���A���̃N���C�A���gPC���璼��WWW�u���E�U��ʂ��Ă����̉f�����A�Đ��A�����A�ҏW�A�Ǘ��ł���Ƃ������̂ł���BWWW�u���E�U��ʂ��āA������ҏW���������Ă���_�ɓ���������B���̃V�X�e���ɂ����ẮA�l�b�g���[�N��ɂ���X�g���[�~���O�R���e���c�ɑ��ă��^�f�[�^��t�^�ƁA�����A�ҏW�Ȃǂ̍��ڂ��B������Ă���B
����ɁA�X�g���[�~���O�R���e���c�݂̂������Ă���V�X�e����Partage��3�j������B����́A�c��`�m��w��w�@����E���f�B�A�����Ȃ̔��m�ے��P�N�J�����T�����J�������V�X�e���ł���BWWW��ɂ���X�g���[�~���O�R���e���c���A���[�U�[��Partage�T�[�o�[��ʂ��ĉ{������BPartage�T�[�o�[�ł́A���[�U�[�͊e�X�g���[�~���O�R���e���c�����Ȃ̍D���Ȓ����ɃJ�b�g���A�܂������̂�����J�b�g�����X�g���[�~���O�R���e���c���D�݂̏��Ԃɕ��בւ��āA����������̃R���e���c�ł���悤�ɉ{�����邱�Ƃ��ł���悤�Ȃ����݂ɂȂ��Ă���B�X�̃X�g���[�~���O�R���e���c�́A�R���e���c���L�҂̃T�[�o�[����{���̓x�ɒ��ڔz�M�����B�]���̈�������̎��Ƃ����ł͂Ȃ��A�������k�̔��\�p�Ȃǂɂ����p���邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�X�g���[�~���O�R���e���c���A���t�⎙�����k���ꂼ��̗v���ɂ�����������g�ݍ��킹�ɕ��בւ��邱�Ƃ��ł��A����ɁA�e�������k��e���t���A�������A���o���A�Ȃ����킹�č쐬�����A�������̃X�g���[�~���O�R���e���c�̂����܂���A���̊e�������k�⋳�t������ɂ������������A�{���ł��邱�Ƃ��\�ɂ��Ă���B
�C���^�[�l�b�g��ɂ���f�W�^���R���e���c�ɂ��āA���ݗ��p��ړI�Ƃ����V�X�e����HTS�iHyper Transaction System�j������BHTS�́ATed Nelson��������Transclusion�ATranscopyright�Ƃ����l�������A���������V�X�e���ł���BTransclusion�Ƃ́A�C���^�[�l�b�g��̑��l�̑n�앨�̈ꕔ��S�����A�C���^�[�l�b�g��̎��Ȃ̑n�앨���Ɍf�ڂ���ہA���l�̑n�앨�̕��������Ȃ̑n�앨�ɓ\��t����̂ł͂Ȃ��A�{������҂ɑ��āA���̕�����n�앨�̂���I���W�i���T�[�o�[�փA�N�Z�X�����ĉ{������悤�ɂ���l�����ł���B�iTed1998�j�{���҂́A����n��҂̑n�앨�����Ȃ���A�����ɑ��l�̑n�앨�����݂���ꍇ�A���̑n�앨�Ɋւ��ẮA���̃I���W�i�����앨���{�����Ă��邱�ƂƂȂ�BTranscopyright�́A����Transclusion�̌`�Ŏ��Ȃ̑n�앨�̗��p��F�߂�Ƃ����ł���BTransclusion���s���ĕ\�����Ă��鑼�҂̑n�앨���A���Ȃ̃l�b�g���[�N��̑n�앨��ɒu�����Ƃɂ��A�����̉{�����������f�W�^���R���e���c�����Ȃ̗v���ɂ����������A�g�ݍ��킹�ȂǂŌ����邱�Ƃ��ł���B�܂��A�n�앨�̒��쌠���́ATransclusion���s���ۂɁA��ʏ�ɂł���悤�ɐݒ肳��A����҂̌����ɔz��������Ă���B
Merlot��4�j�̓A�����J�̍�����������̃I�����C�����ނ�e�Ղɗ��p�ł���悤�ɒ��Ă�����̂ł���B�w�K�I�u�W�F�N�g�������ł���̂ł͂Ȃ��A�����鋳��p�f�W�^���R���e���c�̌f��Web�Ȃǂ̃����N�������Ă���B�����I�Ȃ̂́A���p�҂͂��̃I�����C�����ނɑ��Ă��݂���peer review���s���Alearning community���`�����A�R���e���c�̗��p���ʂ⎿�����߂Ă��邱�Ƃł���B�܂��A�����҂́A���Ȃ̃R���e���c���o�^�����ƁA����I�Ƀ��[���Œm�点����B
�ȉ��ɂ����̊����̃V�X�e���̒B�����ڂ�����B
a�j IEEE�ɏ�������LOM�iLearning Object Metadata�j���w�K�I�u�W�F�N�g���W���[���ɕt�^���āA�L�[���[�h�Ȃǂɂ�錟�����\�ł���iNicer, MPEG Archive Station�j
b�j �L�[���[�h�ȊO�̌��������i�����҂̑����A�ړI�Ȃǁj�ɓK�����������ʂ̕\�����A�\����������������Ă���A���ȏ��̖ڎ��ɏ�������LOM��t�^����(Nicer)
c�j �K�v�Ȋw�K�I�u�W�F�N�g���W���[�������𒊏o���{�����邱�Ƃ�e�Ղɉ\�ɂ���i�Ⴆ��Web�u���E�U��ʼn\�ɂ���Ȃǁj(MPEG Archive Station, Partage, HTS)
d�j ����ɔ����o�����w�K�I�u�W�F�N�g���W���[����v���ɉ����Ă������g�ݍ��킹�āA�D���ȏ��ōD���ȂƂ��ɉ{�����邱�Ƃ��\�ɂ���(MPEG Archive Station, Partage, HTS)
e�j �w�K�I�u�W�F�N�g���W���[���̑g�ݍ��킹���L�����A����ɑ��Ă�LOM��t�^�������\�ɂ���(Partage)
f�j �w�K�I�u�W�F�N�g���W���[���ɂ��āA���p�҂��]���������Ă����A�]���V�X�e���������(Merlot)
g�j �f�ڂ���Ă���w�K�I�u�W�F�N�g���W���[���ɑ��Ă̒��쌠������ʏ�ŕ\������(Nicer, Partage, HTS, Merlot)
h�j �w�K�I�u�W�F�N�g���W���[�����V�X�e���ɗ��p����Ă��邱�Ƃ������������[���Œm�点��(Nicer, Merlot)
�@�ȏオ�A�f�W�^���R���e���c��ʂɑ��Ď�������Ă��鍀�ڂŁA����ɁA�ȉ��̂悤�ȍ��ڂ��X�g���[�~���O�R���e���c�ɑ��Ď�������Ă���B
i�j �����҂́i�܂��͌����҂̃R���g���[�����ɂ���j�X�g���[�~���O�T�[�o�ȊO�ɂ́A�X�g���[�~���O�R���e���c�̕����������Ȃ��悤�ɂ���iPartage�j
3.2�@������������ɂ�����X�g���[�~���O�R���e���c�z�M�E���p���f��
3.1�ŏq�ׂ����ڂ��A��s�����ŒB������Ă���ƍl������B�����̍��ڂ������ėp�I�ȃX�g���[�~���O�R���e���c�z�M�E���p�V�X�e���͈ȉ��ł���B
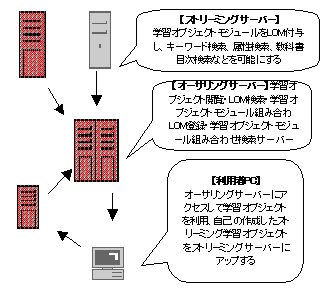 �i�}1�j�����̃V�X�e���̋@�\�������V�X�e��
�i�}1�j�����̃V�X�e���̋@�\�������V�X�e��
LOM�ɂ́A����҂̏���A���̑��̒��쌠��L�ڂ����B
����ɁALOM�̕]���ɂ��āALOM������ʂɂ����āALOM�ɑ���]���Ȃǂ��f�ڂ��Ă����A�������ʂȂǂɂ����f������B
�}1�Ŏ������V�X�e���T�O�}�ł́A��l�b�g���[�N�^�f�W�^���R���e���c�ł͂Ȃ����Ȃ������A�X�g���[�~���O�w�K�I�u�W�F�N�g�����������Ԃ�ꏊ�ɂƂ��ꂸ���R�ɗ��p�ł��邱�Ƃ�A�X�g���[�~���O�w�K�I�u�W�F�N�g���t�̊Ԃł��݂��ɑ��ݗ��p���邱�Ƃ��\�ł���B
�������ALOM�ɒ���҂̏���A���쌠�����L�ڂ��������ł́A�����҂̕ی�Ɍ����A�L���R���e���c�����r�W�l�X����́A�R���e���c�̒��邱�Ƃ͓���B����ɁA�L���R���e���c�̒҂ł͂Ȃ��Ă��A���ǂ��ŒN�����Ȃ̃R���e���c�𗘗p���Ă��邩�ɂ��ď��̒������Ƃ����v�]������ƍl������B�܂��A���݂̗L���R���e���c�̗��p�ɍۂ��āA�w�Z�ɂ�����\�Z�Ǝ��ۂ̉��i�ɊJ��������A�w�Z�ł������w������]�T�͂Ȃ��B�������A�r�W�l�X���Ƃ��ẮA�����ł͐��藧���Ȃ��B�����ŁA�V�X�e���̍��ڂɁA
j) �����҂��A���Ȃ̃R���e���c�̗��p���I���^�C���Ŕc���ł���悤�ɂ���
k) �I���^�C���Ŕc���ł��闘�p�ɍۂ��āA�����̗��p�P�ʂɑ��āA�����ۋ����\�ɂ���
�Ƃ������ڂ�lj����邱�Ƃɂ��A��L�̖�肪��������A���쌠�҂̌����ی�������̃V�X�e����苭�����Ȃ�����A���p�҂̗��v�ɔz�����A�f�W�^���R���e���c�̗��ʂ̑��i�ɂ�����L�p�ƍl�����郂�f�����\�z�����B
3.3�@������������ɂ�����X�g���[�~���O�R���e���c�z�M�E���p���f���Ɋւ��钘�쌠�@�̊ϓ_����̍l�@
���쌠�@�̊ϓ_����l���āA������w�K�I�u�W�F�N�g���W���[�����A�{���҂̃j�[�Y�ɍ��킹�āA����������̍�i�ƂȂ�悤�ɉ{���\�ɂ��邱�Ƃ����쌠�@��ǂ�������̂��l����K�v��������B���ƂȂ�̂́A���ꐫ�ێ����ł���B���ꐫ�ێ����́A����҂��u���̈ӂɔ����āv���앨�́u�ύX�A�؏����̑��̉��ς��Ȃ��v�����ł���B�u�ύX�A�؏����̑��̉��ρv�ƋK�肳��Ă��邪�A�����ƈقȂ�������̉��Ɏʐ^���f�ڂ������Ƃ����ꐫ�ێ����̐N�Q�ƔF�肳�ꂽ����i�����X�N�P���R�O�������u�Ñ��ՐΊ_�ʐ^�v�����j�����邽�߁A�e���Ⴒ�Ƃ̔��f���K�v�ł���Ƃ�����B����̂悤�Ȏ����ƈقȂ�������A�X�g���[�~���O�w�K�I�u�W�F�N�g���W���[�������X�Ɖ{������ꍇ�ɂ����čs����Ƃ͍l����B�܂��A�{���҂��w�K�I�u�W�F�N�g���W���[���𗘗p���Ă��邱�Ƃ𗝉����Ă���̂ŁA���̊w�K�I�u�W�F�N�g���ǂ̒P�ʂ܂ł��N�̒��앨�ł���̂����l�����邱�Ƃ͂��قǓ�����Ƃł͂Ȃ��B�u�ӂɔ�����v���ǂ����ɂ��Ă̔��f�́A����҂̎�ς��̂��̂Ƃ��������A�@�I���萫�̌��n����A���̕���̒���҂̗��ꂩ��݂āA�펯�I�ɁA���̂悤�ȉ��ς͒���҂̈ӂɔ�������̂ƒʏ팾���邩�ǂ����̊ϓ_���画�f����ׂ��ł���i���2002�j�B����āA�X�g���[�~���O�w�K�I�u�W�F�N�g���W���[����������g�ݍ��킹�ʼn{�����邱�Ƃ́A���ꐫ�ێ����N�Q�Ƃ܂ł͌����Ȃ��B�������A�X�̎���ɂ����Ĕ��f�������܂��ɂȂ�\��������̂ŁA�{���f���̗��p�K��A���쌠�҂ɑ���_��ȂǂɁA���̎|���L�ڂ���K�v��������B����ɁA�X�̊w�K�I�u�W�F�N�g���W���[���̉{���ɂ������āA�����̏o����\������K�v�������邪�A�N���W�b�g�Ƃ��Ċe���W���[���̍Ō�ɕ\�����邱�Ƃ͍l����̂ŁA���炩�̕��@�ŕ\�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�ƍl����B
4�D�܂Ƃ߂ƍ���̉ۑ�
�{�����ł́A������������ɂ�����X�g���[�~���O�R���e���c�z�M�E���p���f���𖾂炩�ɂ����B�����̃l�b�g���[�N�����f�W�^���R���e���c�z�M�E���p�V�X�e�����������A�����ŒB������Ă��鍀�ڂ����A�܂Ƃ߂��B�����āA�����S�Ă̍��ڂ����Ė������V�X�e���𖾂炩�ɂ��A����炪�A��l�b�g���[�N�^�̃f�W�^���R���e���c�Ɣ�r���āA�������k�̊w�K�I�u�W�F�N�g�̎��R���p�A���t�̊w�K�I�u�W�F�N�g���ݗ��p���\�ɂȂ��Ă���_���w�E�����B����ɃX�g���[�~���O�R���e���c�̓��������A���ɒ��쌠�҂Ɨ��p�҂̗��v�o�����X�̕ۂ��ꂽ�V�X�e���̎����̂��߂̍��ڂ����������B
������v���ɂ���ĕs�����Ă���Ƃ����Ă��鏉����������ɂ����鋳��p�f�W�^���R���e���c�̗��p�ɑ��āA�V���Ȃ郂�f���̒�Ă��ł����Ƃ�����B
�������ALOM�̕t�^�ɓ������Ă̌����A���A���ۂ̋�����ʂɂ��ẮA�X�Ȃ錟�����K�v�ł���B��̓I�ɂ́A�w�K�I�u�W�F�N�g���W���[���̎��ԓI�����̊�̍쐬�A���ALOM�̍��ڂɂ��Ă̍Č����i�L�[���[�h�̑I�o�̎d���A���ȏ��̖ڎ��ɑΉ����Ă��邾���ł͂Ȃ������鎙�����k�A���t�̗v���ɑ��錟�����ʂ̕\���̂��߂�LOM�Ȃǁj�Ȃǂł���B�܂��A�I���^�C���ɔc���ł��闘�p�ɑ��āA�������p�P�ʂŁA�����̉ۋ����l����ꍇ�A���̋��z�����ƂȂ�B���ȏ��������Ŕz�z�����`������ے��ɂ����Ă͓��ɁA���̋��z�ɂ��āA�����҂Ɨ��p�҂̗��v�o�����X���l�����ۋ��̋��z��x�ݒ肪�K�v�ł���B����ɁA�]���V�X�e���ɂ���āA���̊w�K�I�u�W�F�N�g�ɑ��鎿�Ȃǂ̃����C�A�r���e�B�͕ۂ����Ƃ��Ă��A�����́A���p�҂̗��p���₷���ȂǂɊւ�����̂ł���B�w�K�I�u�W�F�N�g�̎��i�ϗ����Ȃǂ��܂߂��j�A�ʁA�f�[�^�̑����Ȃǂ̊Ǘ��ALOM�t�^�Ɋւ���Ǘ��Ȃǂ̐ӔC�̏��݂����@�ւ��K�v�ł���i��̓I�ɂ́A�I�[�T�����O�T�[�o�[���Ǘ�����Ȃǁj�B����ψ���P�ʂȂǂŁA�C���g���l�b�g���\�z���A����ɃT�|�[�g�Z���^�[�Ȃǂ�݂��āA�e�w�Z�̃T�[�o�[��t�@�C�����u���W�����ĊǗ�����悤�ȃZ���^�[��݂��邱�Ƃ��i�߂��Ă���B�iJAPET�ue-Japan�\�z�U�v�����ψ���2004�j���̂悤�ȃZ���^�[�ɂ����āA�I�[�T�����O�T�[�o�[�Ȃǂ��Ǘ�������Ȃǂ��l������B�܂��A�V�X�e���̗��p��o�^���ɂ��āA���p�҂ɑ���K��A���쌠�҂ɑ���_��Ȃǂ̐�����i�߂Ă����K�v��������B
��
��1�jhttp://www.nicer.go.jp/
��2�jhttp://w3-mcgav.kddilabs.jp/mpeg/marc/
��3�jhttp://partage.sourceforge.net/
��4�jhttp://www.merlot.org/Home.
po
�Q�l����
�������i, �g�y�F��, ���䈟��, �O���F���i2004�j�͐�����{�݂Ƃ̘A�g�ɂ�铮��R���e���c��p�������ȋ���̎��H. ���{����H�w��_����, 28(Suppl.) : 275-280
��㗝��q�i2005�j�d���[�j���O�ɂ������O�Ғ��앨���p�Ɋւ���l�@-���쌠�@��35���ɂ�����_�E�����[�h�ƃX�g���[�~���O-.�@���{�R�G�V�ق��i�ҁj�C���^�[�l�b�g����̒��쌠.�@�c��`�m��w�o�ʼn�,�@�����i2005�N4�����s�\��j
JAPET�ue-Japan�\�z�U�v�����ψ���i2004�j�|�X�g2005�N�Ɍ������u����̏�v�̉ۑ�ƒ�.�@�Вc�@�l���{����H�w�U����,�@����, 41
����U�����Ƌ���iIPA�j,�@�����{�d�M�d�b�������,�@������ЃG�k�E�e�B�E�e�B�E�G�b�N�X,�@������Г��{���j�e�b�N,�@�w�Z�@�l�Y�Ɣ\����w�i2001�j�w�K�I�u�W�F�N�g�E���^�f�[�^�����(Ver1). https://www.alic.gr.jp/activity/2000/iop/wg3_1.htm
�T�����q, ���c�����i2003�j�f���N���b�v��p�����Љ�Ȃ̎��Ɛv-�N���b�v�̗��p�Ƃ��̒��@-. ���烁�f�B�A����, 9:2:61-73
�{��C��i2004�j��3��e-learning�̃R���e���c.�@���{�q�Y, �����G��, ���R���b�i�ҁj,�@e���[�j���O�̗��_�Ǝ��ہ@�V�X�e���Z�p����A�����E�w�сA�r�W�l�X�Ƃ̓����܂�.�@�ۑP�������, ����, p3
�����Ȋw�ȁi2003�j����15�N�x�����w�Z�ɂ�������̎��Ԓ���.�@http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/07/04072101/001.pdf
�����Ȋw�ȁi2004�j�w�Z����̏�̍���̎p�ɂ���-2006�N�x�ȍ~�̊w�Z����̏�ɂ��� -.http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/027/shiryo/05012101/002.htm
��ԕ��Y�i2002�j�ډ��@���쌠�@.�@���傤����, ����234
�����N�h,�@�|�{���i2002�jNICER�ɂ�����w�K�I�u�W�F�N�g�E���^�f�[�^LOM�ƌ����V�X�e��.�@���{����H�w���18��S�����_���W, 4-3-6-3 ,�@845-846
�����O��, ��_���i2004�j�f���N���b�v��p�������j�w�K�ɂ�����T�O�}�ɂ��]��. ���{����H�w����W: 04-5
Theodor Holm Nelson�i1998�j Transcopyright: Pre-Permission for Virtual Republishing. Project Xanadu, Keio University and University of Southampton : http://www.xanadu.com.au/general/transcopy.html
�g�y�F��, ���䈟��, �R�c��s, �������i, �O���F���i2004�j�͐�̗��ʕϓ����f���������W���V�X�e���������ɋy�ڂ��e��.���{����H�w��_����, 28(Suppl.) : 237-243
�ӎ�
�{�����ɂ������āA�V�������_����ɗ^���Ă����������c��`�m��w�F�⌫�������A�_���̍\���Ȃǂ���ׂ������w�������������c��`�m��w��w�@�c�����i�����ɂ́A�[�����ӂ̈ӂ�\���܂��B
Summary
This paper revealed the streaming content delivery and the utilization model in the elementary and primary education. The utility of the streaming content was clarified by comparing with non-network type moving�@picture content. And extracting the each function achieved in existing digital content delivery and the utilization model, the model came out by aggregating these functions. In addition, concerning the balance of those stakeholders (copyright owners and students, teachers), the function which have copyrights owners figure out utilization aspects and which can allow copyrights holders to cost users micro money. And interpreting the copyright law, streaming is said to be "interactive transmission" and �gdownloading" is said to be "reproduction". So, less tight agreement or contract can be made for streaming compared with downloading .