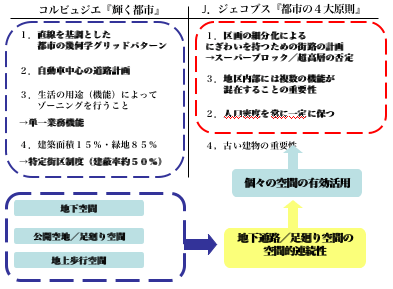
4.研究の方法論
(1) 計画理論の整理
コルビュジエ/J.ジェコブスの計画理論に基づき、新宿副都心区域の現状と、改善点の位置づけを行う
ー コルビュジエの『輝く都市』のモデルー
1947年、パリ現代建築社から出版された、フランス建築家ル・コルビュジエ(1887〜1965)の『輝く都市』(Radiant City)は、彼の都市的理念を語ったものである。
直線を基調とした都市の幾何学グリッドパターン
生活の用途(機能)によってゾーニングを行うこと
自動車中心の道路計画
建築面積15%・緑地85%→特定街区制度(建蔽率約50%)
という考え方を示している。まさに、この考えに基づいて計画されたモデルケースが新宿副都心区である。
ー J.ジェイコブスの『アメリカ大都市の生と死』ー
< ジェコブスの四大原則>
J.ジェイコブスは、アメリカの大都市の再開発における、コルビュジエの『輝く都市』的な要素を用いた超高層の計画を否定し、
1.生活する人々がにぎわいを持つための街路の計画
町中のブロックは短くなければならない。
街路を曲がる機会が頻繁でなければならない。大規模なブロックや、スーパーブロックのつくる長大な街路は、通りの密度を低下させ、個々の街区を孤立させる傾向がある。街路と街路は互いに分断されてしまう。
小規模ブロックが編み出す街路の網の目は、同じ目的地を目指す何通りもの道筋を用意する。
→通路の複雑性ではない!!
→新宿西口で、以上の役割を担うのは地下通路である。
→地下『通路』から地下『街路』への転換
→地下通路ム公開空地/足廻り空間ム地上空間
→スーパーブロック/超高層の解決の一つ
街路の交わる街角は人々の出会いの場となり、そこは活発的な経済活動の場となりやすい。
2. ゾーニングによる単一機能の計画を否定し、地区内部には複数の機能が混在することの重要性
3. 古い建物の重要性
4. 人口密度を常に一定に保つような空間をつくることで、安全性、経済性を確保することができること、
を説いた。
<都市の多様性>
ジェコブスによれば、都市とは「経済的にも社会的にも、互いに支え合う、非常に入り組んだ木目の細かい用途の多様性を持った都市」の事であえる。
計画によってつくられたプロムナードなどは、得てして通路としての用途しか持たないものであるのに対し、まちの商店街は通路でもあれば買い物の場でもあり、さらには情報交換の場でもあるような、様々な用途を持っている。このような用途の多様性が場所に活気を与える。
新宿副都心は、彼女のいう4大原則のすべてを否定した計画である。
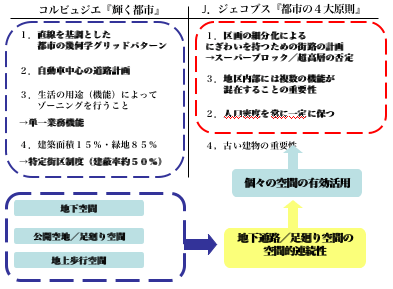
*3 コルビュジエ/ジェコブスの都市論の比較と関係について
(2) 空間評価の観点
芦原義信『外部空間の設計』の空間指標をもとに、地下空間及び、公開空地/足廻り空間の空間分析を行う
分析の要素
1.高低差:階段や斜路の領域
2.空間の閉鎖:閉鎖性による求心的な空間の秩序
(壁の高さ,視線の高さ,壁と壁の距離)
3.PNースペース:外部空間/内部空間.
〈高層街区におけるP,PN,N spaceの定義〉
P space →内部空間
PN space →内部から、または内部への働きかけのある外部空間
N space →内部から、または内部からの働きかけのない外部空間