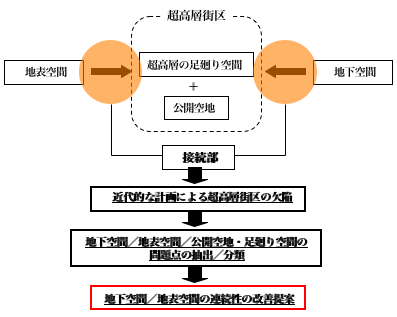
2.研究の目的
新宿副都心区域における地下空間/公開空地・足廻り空間/地表空間の接続部に着目し、空間的問題点とその評価指標を明らかにし、歩行空間のモビリティ、既存の商業空間を含めた足廻り空間/公開空地と歩行空間の連続性を改善する一提案を行うことを目的とする
3.研究の論文構成
本研究は以下によって構成される。
第1章においては、まず、新宿西口副都心区域超高層街区の概要、現状、問題点の整理を行う。
第2章では、第一段階として、新宿副都心区域、地下空間における既往研究を整理し、本研究の意義を明確にする。次に、副都心区域の計画理論として用いられたル・コルビュジエ氏の『輝く都市』注1)と、その理論に対峙して用いられるジェーン・ジェコブス女史の『アメリカ大都市の生と死』注2)を比較し、本研究の目指す方向性を定める。また、芦原義信氏の『外部空間の設計』注3)を参考に、空間評価指標としての観点を得る。
第3章では、対象地区の超高層ビル10事例、及び新宿西口地下街の個々の現状、問題点、を明らかにし、以下の3つの空間について、外部空間・内部空間/高低差/空間の閉鎖性を視点として分析し、問題点の抽出/分類を行う
(1) 各街区の公開空地/足廻り空間の空間分析
(2) 地下空間の空間分析
(3) 地下/地表空間の接続部の空間分析
第4章では、3章で得られた空間分析の結果をもとに、各ビルの空間の連続性に関しての改善提案を行う。
第5章では、第1章から第4章までの分析結果を総括する。その上で、超高層街区における空処理の評価の有効性を示し、今後の新宿をはじめとする、超高層街区の活性化計画のあり方について言及する。
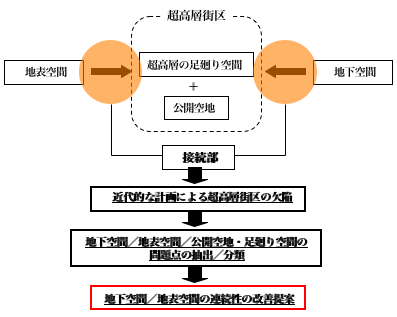
*2 研究のフロー