2007年度森泰吉郎記念研究振興基金 報告書
動詞の使い分けの発達と第一言語の干渉に関する研究
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 佐治伸郎
活動の概要
本研究テーマは子どもが(1)動詞の使い分けをどの様な過程を経て,何を手がかりに学習するのか、(2)またそこに母国語/第二外国語の影響はどれ程働くものなのかに焦点を当てるものである.2007年度は主に(1)の問題を取り上げ,中国語の子どもが持つ/運ぶ系の動詞の使い分けを如何に学習するか,実験的手法を用い調査した.結果として子どもが似たような意味を持つ複数の動詞の使い分けを学習する際.複数の動詞によって表されうる動作のあいまい性を如何に大人と同じような仕方で解消するかが重要な要因になりうることを明らかにした.本森泰吉郎記念研究振興基金の支援を受けた本研究に関連する業績に関してはページ末の活動実績報告を参照されたい.
尚,以下に示す研究成果は主に日本認知言語第8回大会,12th International Conference on the Processing of East Asia Related Languages (PEARL)での発表を要約したものである.
研究成果
1.問題の所在
子どもが「語の意味を学習した」と言うとき,一体それは子どもが何を出来る様になったことを指すのであろうか.この問題に関し従来,言語獲得研究において子どもの語彙獲得の進度を測定する最も基本的な指標は語の産出頻度であった.しかし一方で語の意味を学習という問題を考える際,一つの語を産出するか/しないかといった単純な指標のみではなく,似たような他の語との関係を大人と同じように理解しているか/いないかという視点は非常に重要である.例えば子どもが日本語における「切る」という語の意味を大人と同じように理解するためには,ある動作に対して「切る」という動詞を適切に産出できるだけではなく,大人であれば「壊す」「割く」など動詞を用いるような他の動作に対して「切る」ではなくこれらの動詞を産出出来なくてはならない.本研究ではその様な語と語との使い分けの関係を子どもがどの様な過程を経て理解するか,中国語の持つ/運ぶ系動詞を取り上げ,実験的手法を用い調査する.具体的には
(A)子どもの動詞使い分けパターンは,どの様な経緯を経て大人に近づくか
(B)子どもが動詞を使い分ける際,どの様な要因が学習のし易さに影響を与えているのか
の二点を特に問題として捉え,分析を行った.
2.実験
事例として取り上げた中国語の持つ/運ぶ系動詞の特徴として,その種類の多さが挙げられる.例えば頭の上でモノを支える”Ding”, 肩で担ぐ”Kang”,手のひらでお盆の様なものを支える”Tuo”など,その種類は20以上にも及ぶ.本研究では刺激としてそのうちから撮影可能でありかつ,子どもにとっても日常的に接する機会の多い13の動詞を選びビデオを作製した(図1参照).

図1:実験に用いたビデオ(一部)
実験はビデオを用い,産出実験と理解実験の2種類に分け行った.産出実験においては3歳(16名),5歳(20名),7歳(21名),大人(大学生:21名)の被験者はそれぞれのビデオを見,最もその動作に適する動詞を答えてもらった.理解実験では大人(大学生:27名)の被験者はビデオと動詞の全てのペアを見,その動詞がビデオを適切に表しているかどうかをYes/Noで答えてもらった.産出実験の結果から年齢群ごとにビデオに対して産出された動詞を集計し,各年齢群の名付けパターンを表したマトリクスを生成した(図2,図3参照).


図2:3歳児の名付けパターン 図3:大人の名付けパターン
これらのマトリクスは大人と子供で,どの様に動作に対する動詞を用いた分類が異なるかを示している.これらの傾向を量的な指標を用い確認する為に,次の二つの問いを設け分析を行った.
以下(A)の問いに関する分析として3-1,3-2,3-3,(B)の問いに関する分析として3-4,3-5を行った.
3.分析
3-1.各年齢群において産出された動詞のタイプの数にはどの様な違いがあるか?
分析を始めるにあたり,まず各年齢群において産出された動詞のタイプ数の平均を比較した.これは各年齢群における被験者が,単純にどれくらいの語を知っているかを見る指標になる.結果は以下図5の様になった
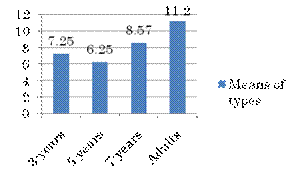
図4:産出された動詞のタイプ数
ボンフェローニ補正法にを用いて補正したt検定を実施したところ子ども同士のペアにおいて有意差は見られなかったが(all ps>1),それぞれの子どもの群と大人の間では有意差が見られた(all ps>.01).この結果,大人の方が子どもよりも扱う語彙の数が有意に多いことが示唆された.
3-2.子どもの動詞の使い分けはどの様に大人の使い方に収斂するか?
次に,子どものビデオに対する動詞の使い分けのパターンが,どの様に大人に近づくのか(または離れるのか)を見るために,相関分析を行った.手続きとして,まず各年齢グループにおいて,各ビデオに対する産出動詞のベクトルのペア全てから相関行列を生成し,さらに年齢群間で相関行列動詞の相関を取る方法を取った.大人と子どもの分布の相関を図5に示す.
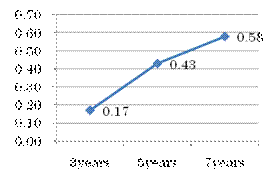
図5:子どもと大人動詞産出分布の相関
子どもの産出パターンは年齢が上がるにつれ,大人との相関を高めている様である.しかしその一方で,(産出頻度自体は大人に近づく)7歳児であっても大人との相関は0.6程度であった.
何故この様に,大人と子どもで分布の形が異なるのか.その一因として,大人が子どもに対して用いる言葉(CDS: Child Directed Speech )の影響が考えられる.つまり大人は子どもとコミュニケーションを取る際より一般的に通用する語,簡単な語を選好し用いている可能性である.この可能性を探るために,2歳児の親と5歳児の親に対し前述の産出実験を行い,大人(大学生)の分布との相関を取った。結果はそれぞれ2歳児の母親:0.81,5歳児に母親:0.83であり,極めて高い相関を示した。このことは,少なくともこの動詞群に対して、大人は子どもに対し簡単な語を選好して用いてはいないことを示している。
3-3.動詞によって収斂の仕方に違いはあるのか
3-1.では子どもの産出動詞の全体に関する傾向が年齢を経るにつれ大人のそれに近づくことを示した。しかしあくまでこれは全体としての傾向であってこの収斂のパターンは動詞によって異なるかもしれない。そこで次の分析では,各年齢群において,各ビデオに対しどの様な動詞が使われているか,その散布度をエントロピー(H)で表現した。エントロピーはこの場合,どれだけ広い範囲のビデオにその動詞が産出されたかを示している。
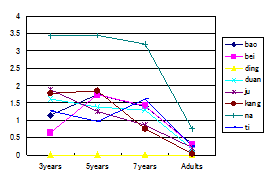
図6:エントロピーの推移
エントロピーは頻度が極端に少ないと散布度を適切に表すことが出来ない.その為,図6では13動詞中全年齢に渡り頻度が5以上であった8動詞を選びエントロピーの推移を示した.示されたエントロピーの推移を見ると,Ding以外の7動詞に関してエントロピーは年齢を経るごとに減少傾向を示している.これは年齢を経るにつれ動詞を適切なビデオに対して産出出来る様になることを示している.しかしその一方で,減少の推移の仕方は各動詞によって大きく異なる.例えばDingに関して,この動詞は全ての年齢群において適切に使い分けられている(Dingという動詞を,こちらがDingと想定したビデオにのみ用いている).一方Naは,3歳,5歳,7歳と過剰汎用されているが,大人ではエントロピー値低く収斂している(但しそれでも他の動詞よりはエントロピー値が高い)。
この対照的な関係は何が原因となっているのであろうか.一つに考えられるのはDingやNaの参照する動作と他の動詞の参照する動作との重なり―つまり動作のあいまい性である.Dingの参照する動作は「頭の上にモノを載せる」という動作であり,他の動詞はこの様な動作を参照しない.その意味であいまい性は低い.一方Naで表される動作は「手でモノを持つ」という動作であり,LinやTiなど他の動詞の参照する動作と重なる部分が大きくあいまい性が高い(分析3-5も参照).このためにDingは他の動詞と重なる部分が少なく,その参照する動作に関して個別の学習ができるのに対し,Naに関しては他の動詞との参照範囲の重なりが大きく、その関係を適切に学習し過剰汎用せず用いるのに時間がかかるのではないだろうかという予測が出来る.
3-4.子どもと大人で動詞を使い分ける手がかりに違いはあるのか
3-3で立てた予測に基づき,もし子どもにとって動作のあいまい性の解消が重要な要因となり得るとすれば,子どもと大人では動作を動詞によってカテゴライズする際に,着目する特徴が異なっている、つまり大人と同じ方法であいまい性を解消していない可能性がある.このことを調査するために,次に分析3-2で用いた相関行列を用いて,INDSCAL(個人差MDS)を行った.個人差MDSは複数のグループにおけるデータ間の距離行列もしくは類似行列を入力とし,出力としてグループに共通する共通次元の抽出,加えて共通次元に関する各データグループの重みづけを算出する方法である.結果を図7,図8に示す.
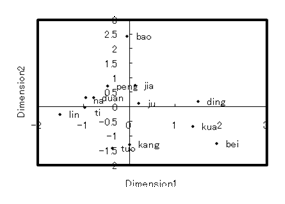
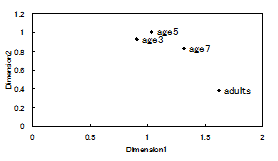
図7:共通空間 図8:個人空間
まず図7の次元に着目すると,第一次元は正の方向にDing,Kua,Bei,負の方向にLin, Na, Tiとあることから,「手を使うか/使わないか」の軸であることがわかる.第二次元は多要因を含んでいると思われるため単純な解釈が難しいが,一つの特徴として正方向にBaoが一つ抜けており一つにはこれを区別する軸である可能性がある.その場合,Baoが他の動詞と明確に異なる点として,今回Baoのビデオには持つ対象となるモノとして「ぬいぐるみ」が用いられていた点を挙げることができる.他のビデオでは箱や,ボウルなどが主に使われていたことを踏まえると,この軸は持つモノの特性を表したものである可能性がある.
次に個人空間に着目すると,大人と子供で,前述の共通空間の各軸に対する重み付けの仕方が違うことが分かる.相対的に大人は第一軸に対する重みが強く,子どもは第二軸に対する重みが強い.このことは,子どもは動詞で持って動作を名付ける際、大人と同じような仕方で動作をカテゴライズできていないことを示している.
3-5.子どもの語の学習のし易さを決める要因は何か
以上の分析を踏まえた上で,最後に子どもが語を学習する際,子どもにとっての語の学習のし易さ/難しさを予測する要因は何か,重回帰モデルによる評価を行った.モデル作成にあたり,本研究で葉二つの「学習のし易さ」を測定する指標を用意した.一つは従来の獲得研究において主な指標とされてきた語の産出頻度である.この指標においては子どもがその語を高頻度で産出しているほど,子どもはその語を良く学習していると見なす.モデル作成にあたり,産出実験における各語の産出頻度を被説明変数に据えた.もう一つの指標は本研究において扱った,子どもが(複数の語の関係を含めて)どれくらい大人と同じように語を扱えているかという指標である.この場合,子どもの語の産出パターンが大人と近ければ子どもはその語を良く学習していると見なす.この指標を被説明変数に据えるために,分析3-2で示した方法で産出実験の結果から子どもと大人の語の産出パターンの相関を取った.
次に説明変数として,3つの変数を据えた.まず語の抽象度を表す指標として,各動詞がどれだけのビデオに対して適応可能か,大人の理解実験の結果からエントロピーを用いて産出した.次に語のあいまい性を示す指標として,各動詞が参照するイベントがどれだけ他の動詞で持って参照可能であるか,これも大人の理解実験の結果からエントロピーを用いて産出した.最後に,子どもがインプットとして得る語の頻度として,Beijing Language Institute,1986における13動詞の産出頻度を産出し説明変数に加えた.以下三つの説明変数,二つの被説明変数を用い二つのモデルを作成した.
結果得られた偏回帰係数を表1(産出頻度モデル),表2(相関モデル)の順に示す,
|
|
3歳児 |
5歳児 |
7歳児 |
|
あいまい性 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.48* |
|
頻度 |
0.42* |
0.60* |
0.49* |
|
抽象度 |
0.64 |
0.40 |
0.59 |
表1:産出頻度モデル
産出頻度モデルにおいては,全てのモデルにおいて頻度の係数が有意となり,値が正方向に大きいことから,周りで高い頻度で用いられる語ほど,子どもは高頻度で産出できることを示している.同時に有意ではないが,抽象度の偏回帰係数も高い.様々な動作に対して適応可能な動詞は,その産出頻度自体も高くなる傾向がある.また5歳児においてのみ曖昧性の係数が負方向に有意となっており,3歳児,5歳児と単調現象の傾向にある.これは年齢が進むほど,あいまい性の高い動詞(動詞で示される動作が他の動詞でも参照可能である動詞)を産出する頻度が少なくなることを示している.
|
|
3歳児 |
5歳児 |
7歳児 |
|
あいまい性 |
-0.73* |
-0.81
* |
-0.86
* |
|
頻度 |
0.39 |
0.00 |
0.17 |
|
抽象度 |
0.09 |
0.18 |
0.19 |
表2:相関モデル
相関モデルは産出頻度モデルとは異なった傾向を示した.まず全ての年齢群において有意になったのは動詞の参照する動作のあいまい性の偏回帰係数であり,全て大きく負の値を示した.つまり動詞の参照する動作のあいまい性が高いほど,子どもはその動詞を大人と同じように用いることが難しい.一方興味深いことに,3歳児における頻度の係数は,3歳時と比べ5歳,7歳時には減少する.つまり3歳時では頻度が高い語を大人と同じように用いる傾向があるが,5歳,7歳に関してはその傾向は弱まる様である.
2つのモデルを合わせ考えると,産出頻度モデルの結果から子どもは基本的に高頻度で用いられている動詞を多く産出する一方で,大人と同じように動詞を使い分けるためには動作のあいまい性を解消する必要があり,この結果は3-4の個人差MDSの結果と矛盾しないものであることが分かる.
4.結論
本研究では子どもが複数動詞の使い分けを如何に学習するかを調査するため,(A),(B)の問いを立て分析を進めた.(A)の問いに答える為,3-1,3-2,3-3で示したように,相関分析とエントロピーを指標として用いた散布度分析を行った.結果として,動詞の使い分けは年齢を追うに従って次第に大人に近づくこと,但し大人への近づき方は動詞によって大きくことなる事が示された.次に(B)の問いに答えるために個人差MDS,重回帰分析を行った.個人差MDSの結果,大人と子どもでは動作を動詞で分類する際に用いている特徴(手の重要さ,モノの重要さなど)が顕著に異なる事が分かった.重回帰分析では子供が大人と同じように動詞を使うためには,動詞の参照する動作の曖昧さ(他の動詞の参照する動作とどれだけ被っているか)が重要な要因であることが示された.また興味深いことに,従来の研究において頻繁に使われる指標である子どもの動詞産出頻度を被説明変数に据えた場合,それに寄与する要因は前述の要因と異なるものになった.
以上の様に本研究では,単一の動詞では無く,あるドメインに属する動詞全体のシステムがどの様に学習されるかに焦点を当てて分析を行った.結果として言語獲得において意味の問題を論じる際,単一の語の産出頻度だけでは十分とは言えず,本研究の様な視点を取ることが獲得研究の異なる切り口を提案できる事を示した.
5.活動実績(学会・シンポジウムでの発表)
佐治伸郎, 今井むつみ, Henrik Saalbach (2007.9月) 語彙獲得における動詞の使い分けに関する研究 中国語の「持つ」系動詞を事例として, 日本認知言語学会
第8回大会 成蹊大学
Saji, N.,
Saalbach, H., Imai, M, Zhang, Y., Shu, H., & Okada, H. (December,2007).
Learning verbs as a system: How Child
children learn relations among
carry/hold
verbs. Paper presented at the 12th
International Conference on the Processing of East Asia Related Languages
(PEARL).
Cheng
Kung University, Tainan, Taiwan (December 28, 2007)
Saji, N.,
Saalbach, H., Imai, M, Zhang, Y., Shu, H., & Okada, H. (submitted).
Fast-mapping and Reorganization: Development of Verb Meanings as a System.,
the 30th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Washington,
D.C, USA (July 23-26, 2008)
Saji, N.,
Saalbach, H., Imai, M. (2008, February). How do children sort out relations
among verbs belonging to the same semantic domain? GCOE CARLS
Symposium:General
"Rational Animals, Irrational Humans".