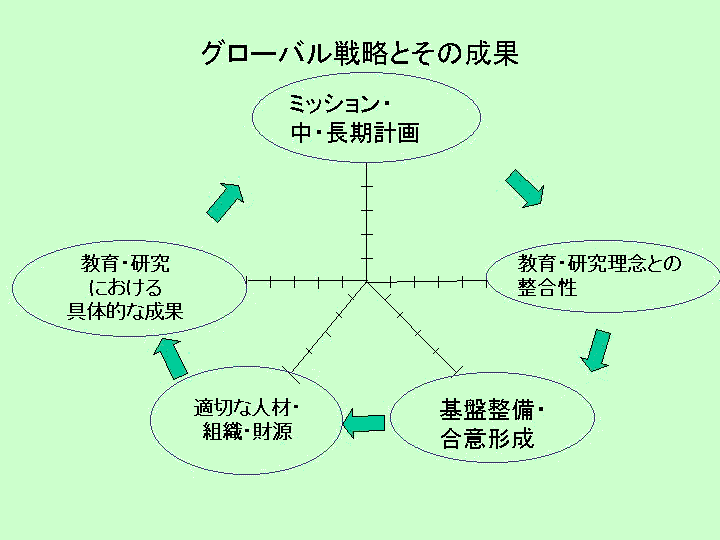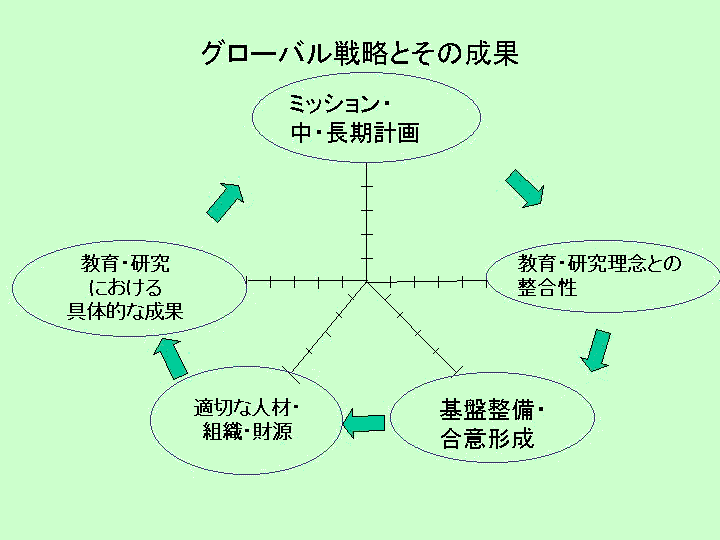IV. <評価チェックリスト>大学グローバル化の指標
高等教育におけるグローバル化の指標についてはまだまだ議論が始まったばかりだ。例えば、興味深いインデックスとしてフィンランドのCenter
for International Mobility (CIMO)が作成した “Checklist for institutional
self-evaluation of internationalization”や「『大学の国際化の指標』の試み」(「大学国際化の研究」江淵一公、二章六節)などがある。こうした指標に共通している課題を簡単に整理すると以下のようになる。
-
個々の大学において、Globalに教育・研究を展開していくことに明確な《価値》を見出すことが重要である。つまり、キャンパス・グローバル化が大学にとって何故必要となっているかを確認するべきである。そのうえで、大学内でグローバル化にむけた《理念》と《戦略》を明文化すべきである。
-
理念と戦略にもとづいて、キャンパス環境をグローバル化する《制度》や《システム》を確立されるべきである。
-
制度やシステムを維持・発展させていくためには、グローバル化を推進する《組織》と≪人材≫が必要である。
この議論を延長させ、何をもってキャンパスがグローバル化した、と評価できるのか、について、基本的なコンセンサスと形成できないだろうか。そのことを通じて、個々の大学でグローバル化の取り組みを自己点検するためのチェックリストのようなものを作ってみてはどうか、とわれわれは考えてみた
以下にわれわれプロジェクトで検討したチェックリストを提案する。もちろん、個々の大学において、グローバル化の計画、方針、戦略は異なっているので、画一的な指標を提示ことは不可能であろう。ここで提案するのは、比較的中規模な私立大学において、これからグローバル化の取り組みを意識的に推進しようとしているケースを想定している。図2においては、こうした大学での一般的なグローバル化の方針が決められ、推進されているサイクルをあらわしてみた。このサイクルのなかで、それぞれのフェーズでチェック項目を設けて、自己評価する方式をとっている。
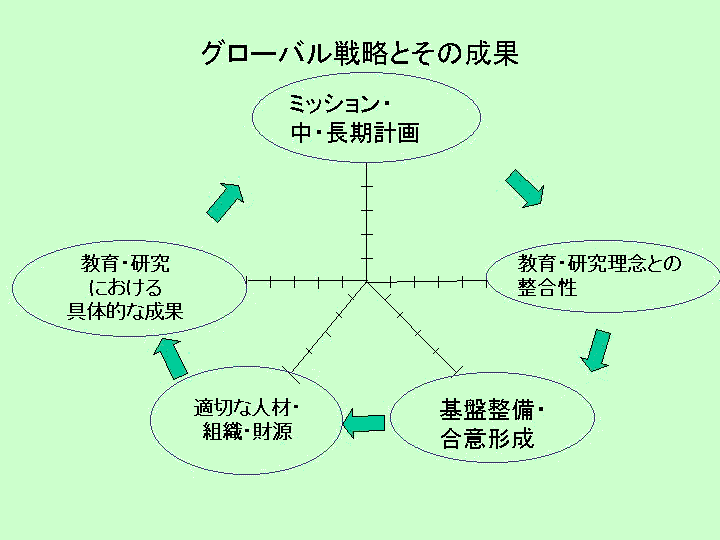
Phase1)ミッション、中・長期計画
-
キャンパス・グローバル化についての指針や中・長期方針が策定されているか?その方針が明文化され、学内で認知されているか?
-
そもそも、「グローバル化」「国際化」とは、どういう状態をめざいしているのか?「グローバル化」「国際化」の理念や目標について、学内での基本的な合意が見られるか?
-
外国人教員数、留学生数、教員海外派遣、学生の海外への留学、交換留学件数、国際共同研究などのについて具体的(数値)目標は設定されているか?
-
現状の問題点を的確に把握する努力をしているか?自己点検項目に「グローバル化」「国際化」に関する事項が盛り込まれているか?
Phase 2)教育・研究理念との整合性
-
「建学の理念」や将来構想がグローバル化の理念と合致しているか?
-
キャンパス環境をグローバル化することに、明確な意義、価値を見出しているか?一般的に留学生数、外国人教員数が増えることについて、明確な意義を見出しているか?
-
海外の提携大学を選ぶにあたって、一定の基準を設けているか?首尾一貫した考え方に基づいてパートナーを選んでいるか?また、地域的な偏りを避けるような配慮をしているか?
-
海外への教員派遣については、戦略的な方針をたてているか?
-
異文化理解、カリキュラムの基本的な課題としているか?
-
協定に基づく学生交換について、大学として積極的に推進しているか?
-
留学した学生の単位認定について、自校での履修を義務づけている科目との、他大学で取得した単位の振り替えとの間に明確な基準があるか(単位振り替えの上限や振り替え可能な科目について明確な基準を設けているか)?
Phase 3)基盤整備・合意形成
-
理事会、教授会などの場で「グローバル化」「国際化」の具体的方針が議論されているか?議論の内容が学内で情報公開されているか?
-
国際化にかかわる委員会(「国際交流委員会」など)が、教授会などの意思決定機関に十分な影響力を持っているか?
-
国際化にかかわる議論に、学内の構成員(教員、職員、学生など広い範囲)が積極的に参加しているか?
Phase 4)人材・組織・財源
-
合意された内容を執行する機関が明確に存在しているか?(ルーチン業務ではなく、あらたに決定された事項を推進しうる機関)国際業務部門が発展的に業務に対応しているか?
-
国際関連業務を執行する部門が他の部門の業務と十分な連携をとって業務を推進しているか?(国際業務部門が、「孤島」となってはいないか?)他部門への影響力を十分発揮しているか?
-
教職員の採用にあたって、国際的な視点で広く募集をおこなっているか?(国際公募の推進など)
-
国際業務に対応しうる人材がバランスよく配置できているか?方針に対応した人事配置をおこなっているか?必要な人材を獲得するためのシステム(リクルートする体制)ができているか?
-
留学生の受入れ、交換留学、学術交流などの分野で、方針に見合った組織体制ができているか?
-
異なる言語、文化的背景を持つ者が協力して働けるような環境整備ができているか?(バイリンガル、または多言語によるキャンパス運営など)
-
グローバル化に対応するFD,SDが方針に基づいておこなわれているか?
Phase 5)教育・研究における具体的成果
-
教員交流の蓄積によって、国際共同研究などの成果が十分見られるか?
-
中・長期方針に基づく具体的な成果が上がっているか
-
キャンパス構成員(教職員、学生)の多国籍化については進捗しているか。
-
留学生受入れは円滑におこなわれているか?海外から志願者に十分な情報提供がおこなえる体制が取られているか?
-
入学案内などの広報活動がバイリンガルまたは多言語で行われているか?
|
|
|
|
……禁無断転載……
Copyright 2000:KEIO Shonan
Fujisawa Campas
E-mail:ashizawa@adst.keio.ac.jp
|