| ▲好熱菌の世界 まず、私が研究対象としている好熱性細菌について説明したいと思う。 現在、微生物から我々人間までを含めた生物は 16SrRNA(リボソーマルRNAの中の一種類、すべての生物にほぼ共通して存在するRNA) の種類を利用した分類方法に基づき、生物の進化系統上、 大まかにBacteria、Archaea、Eukaryaの3つに分類することができる。以下に分類方法を示す。 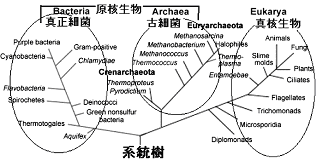 ●真核生物(Eukarya) 細胞の内部に核を持つ生物。人間を含む動物や植物など高等生物を含む集団・原核生物細胞の外側が細胞壁で囲まれ、細胞の内部に核を持たない生物 ● Bacteria(細菌、真正細菌) 一昨年夏に大流行した大腸菌O-157や、胃ガンの原因といわれているピロリ菌等を含む集団 ●Archaea(古細菌) 非常に生物種が少ない。また、古細菌は真正細菌や真核生物にとっては極限環境を生育環境とする事が注目されている。また、生育温度が55度以上である好熱性細菌の多くはこれに属する。 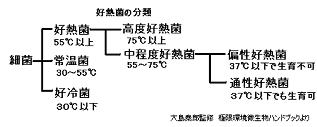 ▲好熱菌研究を通じて考えている目的 好熱性細菌の耐熱性は二つの理由により古くから研究されてきた。 一つ目は、実利性という点である。 摂氏100度を生育環境とするような好熱性細菌。 その耐熱性が解明されれば、様々な化学反応の効率化に応用できる。 化学反応の際に使用される触媒の多くはタンパク質であり、一般的にタンパク質は 高温で活性を持たせると変性し、元のタンパク質とは違った性質を獲得する。 (蛋白質が変性しない上限温度は通常50度程度と言われる) これらの実験に好熱性細菌のタンパク質を利用することができれば、 より高温で反応を起こすことが出来、高温でしか得ることができない生成物を作ることができる。 現在のタンパク質が持つ温度的弱点を克服出来ると言われている。 そして二つ目としては、生物の進化を解き明かす可能性があるという事である。 生物はいつ頃誕生し、どのように進化を遂げてきたのかという点では多くが未だ謎に包まれている。 好熱性細菌は、それ自身が極限環境性を持ち、200気圧以上の深海、摂氏110度を超える火口、 無酸素で窒素しかない場所等に住む種もいる。 この極限環境性が太古の地球と酷似しており、進化の謎を解き明かす鍵に なるのではないかといわれている。 この2点を研究を行う上での大きな目的とし本研究を行う。 |