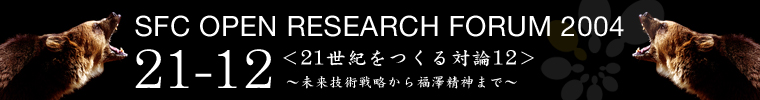 |
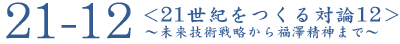 |
12の対論
遺伝子情報からデジタルアースまで、21世紀だからこそ、未知なる情報と環境が膨大な拡がりや多様なスタイルとなって溢れでてくる。その12世界に対し、政策論としていかに果敢に挑戦するかを思考実験する。
|
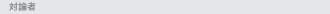 |
 |
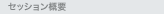 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
相磯 秀夫
東京工科大学学長
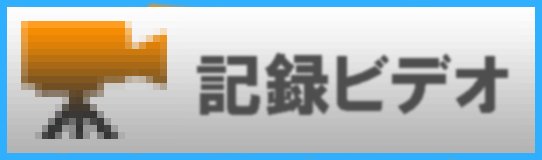
|
 |
村井 純
SFC研究所長
環境情報学部教授 |
 |
井庭 崇
総合政策学部
専任講師 |
|
新しい技術や概念が社会を変え、逆にそれらは社会的影響のもとで開発される―――この複雑に絡み合った流れの先に、私たちの未来がある。本セッションでは、ネットワーク社会の近未来について考える。
|
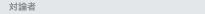 |
 |
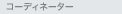 |
 |
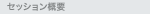 |
 |
 |
 |
 |
徳田 英幸
政策・メディア研究科委員長
環境情報学部教授

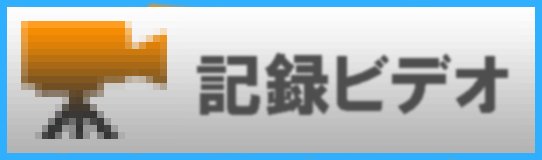
|
 |
曽根 泰教
政策・メディア研究科教授 |
|
 |
 |
神成 淳司
岐阜県情報技術顧問/国際情報科学芸術アカデミー 講師 |
|
三位一体改革に代表されるように、日本の政策は大きな転回点を迎えている。一方、ユビキタス社会に代表されるように科学技術は人々の日常生活に浸透してきたが、科学技術の知見が適用された政策はe-Japan戦略等のごく一部である。日本の国際競争力を高め、地域振興を促進するために、今後の科学技術政策のあり方を論じる。
|
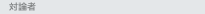 |
 |
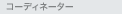 |
 |
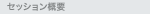 |
 |
 |
 |
 |
久常 節子
看護医療学部教授

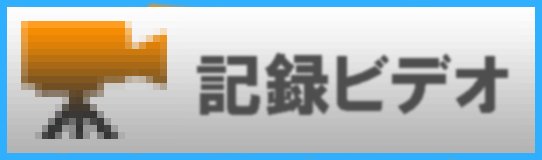
|
 |
堀 茂樹
総合政策学部教授

|
|
 |
 |
福田 亮子
環境情報学部
専任講師 |
|
思想と現場という2つの立場から現在の少子高齢化社会とジェンダー問題を考察し、将来の社会について考える。子供とは何か、高齢者とは何か、そして性差とは何かを考えることで個人化が進む中での共生のあり方を探る。 |
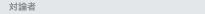 |
 |
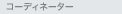 |
 |
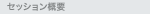 |
 |
 |
 |
 |
清水 浩
環境情報学部教授

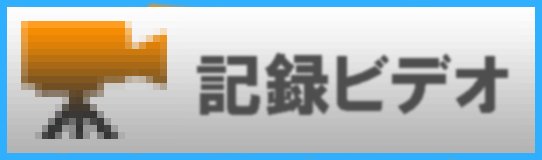
|
 |
小島 朋之
総合政策学部長
教授

|
|
 |
 |
古谷 知之
環境情報学部
専任講師 |
|
地球環境にやさしい技術を追求する立場(清水)と、環境保全と地域開発の間で揺れる東アジアのガヴァナンスを研究する立場(小島)とが、環境(Environment)・経済(Economy)・公平性(Equality)の3Eについて、21世紀的課題を討議する。
|
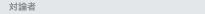 |
 |
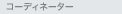 |
 |
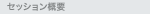 |
 |
 |
 |
 |
草野 厚
総合政策学部教授

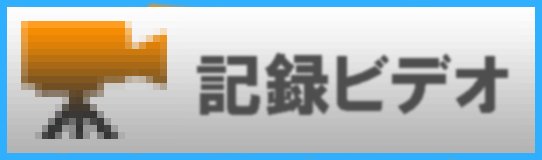
|
 |
坪田 知己
政策・メディア研究科教授

|
|
 |
 |
佐々木 裕一
政策・メディア研究科博士課程 |
|
ネットワークの普及により情報の発信者と発信量は増えた。でもわれわれの処理できる情報量はさして変わっていない。無駄な情報が相対的に増えているというこの現実に向き合い、情報流通・受容の新しいあり方を探る。
|
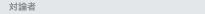 |
 |
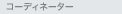 |
 |
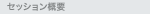 |
 |
 |
 |
 |
福田 和也
環境情報学部教授

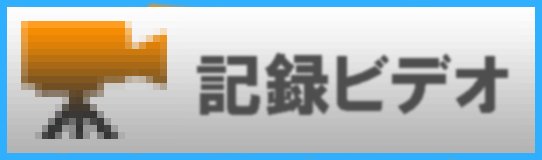
|
 |
奥出 直人
環境情報学部教授

|
|
 |
 |
脇田 玲
環境情報学部
専任講師 |
|
ポップカルチャが作り上げている新しい「個」と「公共性」の問題について、福澤精神の基本となる「独立自尊」との関係性を交えながら議論を進める。また、新しいデジタルメディアとポップカルチャの関係性についても考察を進める。
|
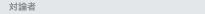 |
 |
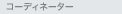 |
 |
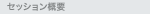 |
 |
 |
 |
 |
竹中平蔵
内閣府特命担当大臣
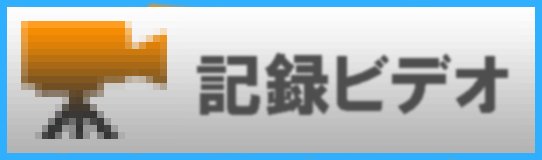 |
 |
金子 郁容
政策・メディア研究科教授 |
|
 |
 |
玉村 雅敏
総合政策学部
講師 |
|
現在、様々な領域で、新たな社会システムへ向けた構造改革が推進されている。そこでは、競争とリスクを前提とした市場メカニズムの活用・設計や、自発性や共創に支えられるコミュニティやコモンズの活用・設計など、多様な切り口や組み合わせが求められている。このセッションでは、新たな社会システム設計の根幹となるものを、理論と実践を兼ね備えた出演者によって紡ぎ出す。
|
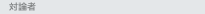 |
 |
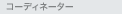 |
 |
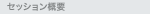 |
 |
 |
 |
 |
榊原 清則
総合政策学部教授

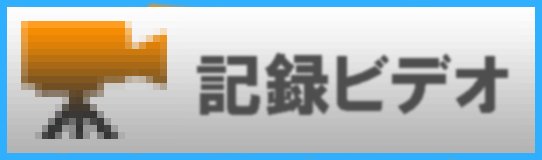
|
 |
國領 二郎
環境情報学部教授

|
|
 |
 |
牧 兼充
政策・メディア研究科助手 |
 |
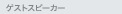 |
 |
 |
佐藤 輝英
株式会社ネットプライス
代表取締役社長兼CEO |
|
共同研究やベンチャーのマネジメントにおいては、公益性と私的利益のコンフリクトが常に内在し、その対応は成功のための必須条件である。本パネルにおいて、具体的な事例を交えながら、その対応策に関する知見を提供する。
|
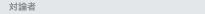 |
 |
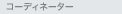 |
 |
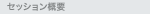 |
 |
 |
 |
 |
古川 康一
政策・メディア研究科教授
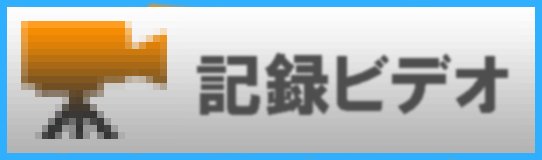
|
 |
村林 裕
東京フットボールクラブ株式会社
専務取締役 |
|
 |
 |
仰木 裕嗣
環境情報学部専任講師 |
|
磨き抜かれたスポーツ選手の技。これをいかにして聴衆にアピールするのかというス ポーツビジネスの視点。いかにして科学的に技能を定量化しこれを新たな知識とする のかという身体知科学の視点。2つの視点が生み出す新たな知とは何か。
|
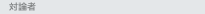 |
 |
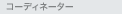 |
 |
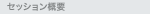 |
 |
 |
 |
 |
浜中 裕徳
環境情報学部教授

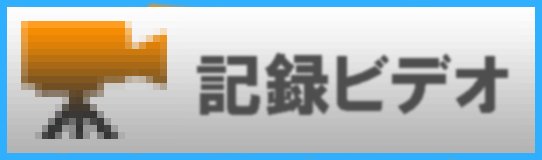 |
 |
福井 弘道
総合政策学部教授

|
|
 |
 |
吉田 浩之
総合政策学部専任講師 |
|
「人は、嘘を信じても、ありそうにないことは決して信じない(ワイルド、1891)」地球環境をテーマとした、政策・行動と空間情報の間の連携と相克についての対論。知る、信じる、行う、そして、それらの間の「ずれ」の有無について考えてみる機会である。 |
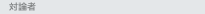 |
 |
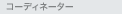 |
 |
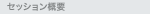 |
 |
 |
 |
 |
冨田 勝
環境情報学部教授

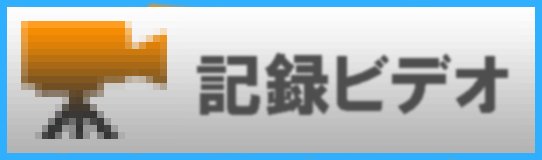
|
 |
野末 聖香
看護医療学部教授

|
|
 |
 |
内藤 泰宏
環境情報学部専任講師 |
|
劇的に増加する遺伝子情報。最先端の生命科学は、情報の集積としてヒトを理解することを目指している。一方で、人の心と向き合う医療の現場は、先端科学に何を期待するのか。生命科学が人間のために解明すべき問題を照らしだす。 |
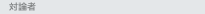 |
 |
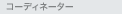 |
 |
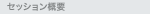 |
 |
 |
 |
 |
奥田 敦
総合政策学部助教授

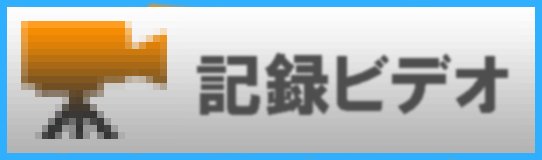
|
 |
野村 亨
総合政策学部教授

|
|
 |
 |
廣瀬 陽子
総合政策学部専任講師 |
 |
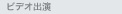 |
 |
阿川 尚之
在アメリカ合衆国日本国大使館公使(広報文化担当) |
|
9・11事件後、世界を西欧文明とイスラーム文明の対立構造で捉える「文明の衝突」論の信憑性が増したかに見える。だが、文明は本当に衝突しているのであろうか?また、もし、それが真だとすれば、我々はそれを乗り越えられないのだろうか。本対談では、その課題を、憲法9条問題、自衛隊問題、イラク戦争、石油問題、人権・民主主義、米国憲法の精神とクルアーン(コーラン)の精神などを鍵として考える。 |
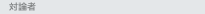 |
 |
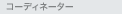 |
 |
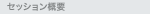 |
 |
 |
 |
 |
村井 純
SFC研究所長
環境情報学部教授

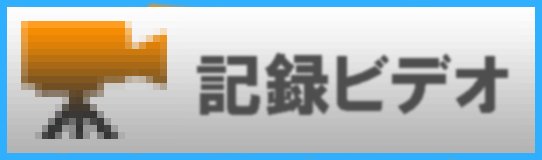 |
 |
坂 茂
環境情報学部教授

|
|
 |
 |
土屋 大洋
総合政策学部助教授 |
|
インターネットのアーキテクチャをデザインする村井純。紙でできた教会など数々の斬新な建築を発表し続ける坂茂。世界を股にかけて活躍する二人が構想する次の社会のアーキテクチャはどのようなものかを語り尽くす。 |
|
|